あわせて読みたい
元陸将「逐次投入がまるで悪い言葉のように使われていますが…」能登半島地震、自衛隊の対応は“批判されて当然”なのか
発災から1カ月以上が経った能登半島地震だが、被災した人々の避難生活は続き、現地の復旧作業もはかどらない状況が続いている。国会では政府の対応の拙さを批判する声が上がり、その矛先の一つは自衛隊に向けられている。「過去の震災と比べて投入した人数が少ない」、「隊員を小出しにする逐次投入だ」といった批判だ。かつて能登半島を含む陸上自衛隊中部方面隊の総監を務めた山下裕貴・千葉科学大客員教授(元陸将)は「自衛隊だけではなく、政府全体で考える問題だ」と指摘する。
逐次投入の是非
元日に発災した能登半島地震に対し、自衛隊は翌2日に約1000人、3日に約2000人が現場で活動し14日から15日にかけて、最大規模の約7000人にまで増やした。この流れが、発災3日目には約1万4000人の自衛隊員が派遣された熊本地震(2016年)などと比較され、「逐次投入」だという批判を招いた。
山下氏は「逐次投入がまるで悪い言葉のように使われていますが、戦場でも逐次投入は立派な戦い方の一つとして位置付けられています。それは敵味方ともに前進中に遭遇して生起する浮動状況での遭遇戦です」と語る。戦場で敵の状況がはっきりわからない態勢で遭遇した場合、味方の部隊を到着順に次々と戦場に投入して、戦況を有利に導く戦術だ。山下氏は「能登半島地震の場合、まさに発災直後は被害状況がはっきりしておらず、遭遇戦と同じ状況にありました」と指摘する。
自衛隊の場合、活動を起こす最初のアプローチとして、地上では小型車両やオフロードバイクなど、上空からはヘリコプターなどを使って戦場や被災地の情報を収集する。この情報収集活動によって、火災や津波の発生状況や土砂崩れ、住宅の被害などを把握することはできる。ただ、目視するだけでは、住民がどのような被害に遭っているのか、何人くらい住んでいるのか、自力で逃げられない人がどのくらいいるのかは、わからない。
山下氏によれば、こうした発災直後の情報の把握は、地元自治体や警察・消防の役割になる。山下氏は「市町村や県、あるいは警察などから情報をもらわないと、自衛隊は情報収集や十分な派遣準備ができません」と語る。
「発災後72時間」の重要性
もちろん、自衛隊も人命救助のタイムリミットとされる「発災後72時間」の重要性は理解している。自衛隊の各駐屯地には、エアカッターや斧、ジャッキ、チェーンソーなどの「災害派遣人命救助セット」が備え付けられている。時間単位で出場できるファスト・フォース(初動対応部隊)が24時間365日の体制で準備している。
まず、ファスト・フォースを送り出し、その間に非常呼集をかけて、他の隊員たちを部隊に戻して準備する。ファスト・フォースは通常、2~3日分の食料しか携行していないため、数日後には派遣隊員を入れ替える必要があるからだ。最初の派遣規模は、こうしたファスト・フォースを中心にした部隊だった。
発災から72時間が人命救助の重要な段階になる。自治体などからの情報提供や自衛隊の偵察活動により救助が必要な地域を特定し、必要な部隊を迅速に逐次投入していくのが災害派遣の鉄則だ。大規模な被害地域には、ある程度大きな部隊を投入する。この場合には自己完結性を担保するために、補給部隊や展開地などの基盤を考慮する必要があるという。
また、実際に隊員の派遣も困難を極めた。山下氏は陸自中部方面総監時代、ヘリコプターで上空から能登半島を視察した経験がある。「能登半島は、山地に小規模な集落が点在しています。集落には、半島を囲むように伸びる海岸線沿いの道路からアクセスする必要があります。ただ、隆起した山地が海岸線まで迫っていますから、今回のように海岸線沿いの道路が寸断されると、大多数の集落は簡単に孤立してしまいます」(山下氏)。実際、今回の震災では徒歩でしかアクセスできない事態も発生している。
熊本地震の際は、近傍に陸自の駐屯地などがあった。だが、能登半島は輪島市に空自のレーダーサイトがあるだけで、「自衛隊の空白地」とされる。一番近い部隊は、金沢市の第14普通科連隊だが、やはり能登半島の海岸線沿いの道路が寸断されたため、すぐに接近できなかった。
自衛隊の災害派遣の基本方針は「国土防衛にあたっての人員や装備を転用する」というものだ。23年3月の時点で、自衛官の定員は約24万7000人だが、実際の現員は23万人程度にとどまっている。定員に対する現員の割合(充足率)は92%程度だ。陸上自衛隊の場合、冷戦時代にソ連の脅威に対抗して北海道を中心に編成していた部隊を、中国の脅威増大に伴い、南西方面に重点的に展開する作業に追われている。
また、これまで財政上の理由から防衛予算の増加が抑制され、財政当局からは陸上自衛隊の部隊縮小・駐屯地の統廃合や自衛官の現員削減などが求められてきた。「なぜ、能登半島に自衛隊をもっと置いておかなかったのか」という指摘はあたらないだろう。
ヘリコプターを使うべきだった?
また、「陸上からの接近が困難なら、ヘリコプターを使うべきだった」という声もある。山下氏は「平野部に隣接した山間地に対する災害派遣だった熊本地震とは、状況が異なります。今回はヘリポートの数も制限されていました。学校の校庭に降りれば良いではないか、という意見もありましたが、被災地に近い場所なのか、災害派遣の拠点地にできるのかなどを検討する必要があります。降りられるから良い、というものではないのです。投入した部隊が孤立しては元も子もありません」と話す。
それでは、なぜ、ここまで自衛隊の災害派遣が問題視されることになったのか。1月24日に行われた参議院予算委員会では、自衛隊派遣の遅れや派遣規模が少数にとどまったことについて、人災の要素があるという指摘が出た。発災直後から、記者団から、自衛隊の派遣規模を尋ねる質問が繰り返された。
防衛省は2日には、陸海空自衛隊による統合任務部隊を編成し、最大1万人規模の態勢をとることを決めた。山下氏は「人命救助を急げという指摘は理解できますが、数だけを問題視するのは短絡的すぎると思います。政治家も批判を避けるため、安易に派遣の人数を約束したり、公言したりするのは控えるべきです」と語る。
山下氏によれば、2018年の北海道胆振東部地震では、政府が自衛隊の派遣規模にこだわり過ぎたため、現場に隊員があふれた。当時、「一つのたこつぼ(1人用の塹壕)に10人も入れということか」という冗談が隊員の間で広がったという。山下氏は「派遣人員数とは、必要な場所に必要な人員を投入した結果で導き出されるものです。最初から投入員数を決めるのは、根拠のない数を示しているということです」と話す。
災害が起きるたびに「これまでの教訓を生かしていない」という指摘が出るが、被害の特徴は全て異なるため、簡単に比較はできないだろう。
カメラの外で起きていること
山下氏は「テレビやネットで流れる映像や情報だけで、簡単に批評することは避けるべきです。画面に映った災害現場や避難所に自衛隊の姿が見えないからといって、『自衛隊は何をやっているんだ』と判断するのは早計です」と語る。カメラが入れないような場所で復旧活動に従事しているかもしれない、という意味だ。
山下氏は「かつてのベトナム戦争では、米国市民がテレビで流れる映像にショックを受け、反戦運動が広がり、米国は戦争を続けられなくなりました。また、議員が作戦に容喙(くちばしを挟む)し、現地部隊が混乱を起こす原因にもなったと言われています。当時の戦争継続の是非は別として、マスコミが発表する一面的な情報だけで全体を判断するのは避けた方が良いと思います」と語る。
衣食住をすべて自己完結できる自衛隊は、頼りになる存在であることは間違いない。山下氏も「自衛隊の演習は、災害派遣とは比べものにならないくらい厳しいものがあります。防御演習では、1週間ほど、塹壕などの陣地に入ったままで、対抗部隊の攻撃を防ぐ訓練をします。警察や消防に比べ、災害派遣が長期にわたっても耐えられる体力と精神力を備えているのは、このような厳しい訓練を行っているからです」と語る。
1月中旬から、被災地の中学生らが石川県南部などに避難する「2次避難」が始まった。専門家の間からは、被災者を安全な後方地域に移した後、災害復旧活動に全力を挙げる方策などを提案する声も出ている。
災害の態様は千差万別だから、簡単に対応の是非を判断できない。ましてや、批判の矛先を自衛隊に絞って向けても、生産的な議論は得られない。今は、被災者の生活の安定と、復旧作業にめどをつけることに全力を挙げる時だろう。
(牧野 愛博)

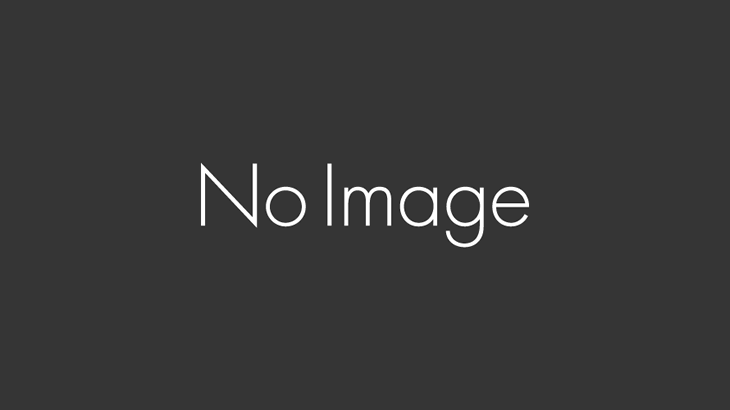








![岸田首相、ジョークで会場沸かせる 日米公式夕食会 [朝一から閉店までφ★]](https://trivia.awe.jp/wp-content/uploads/2024/05/865288.jpg)

