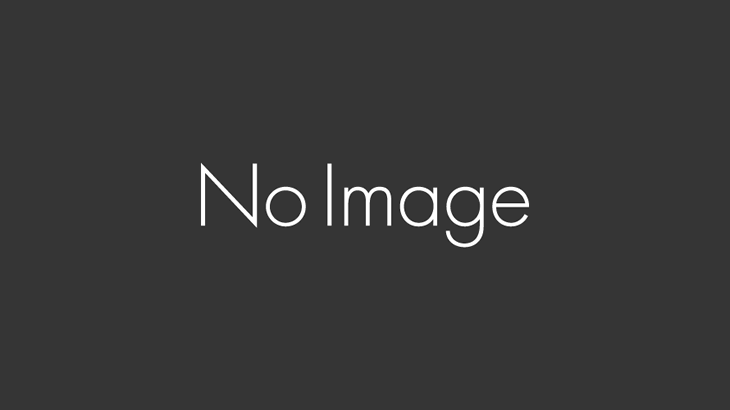あわせて読みたい
40~50代賃金は20~24歳の「2→1.5倍」に急減…中高年いじめの賃上げ格差が回り回って少子化拍車という皮肉
■昇給は平等ではない、企業が若手に手厚くする理由
2024年の賃上げ交渉を前に、早くも賃上げムードで盛り上がっている。労働組合だけではなく、昨年11月の政労使会議では賃上げに向けて経済界も足並みを揃える。
物価の高騰を受けた23年の春闘の賃上げ率は、労働組合の中央組織の連合の発表で前年比3.58%。額にして1万560円だった。これは労働組合のある企業だけの調査であるが、労働組合のない企業が8割を占める厚生労働省の「令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査」(常用労働者100人以上、1901社)によると、賃上げ率は3.2%(前年1.9%)と、現在の調査方法となった1999年以降で最も高かった。引き上げ額は9437円(同5553円)で、連合の集計より低いが、賃上げの動きが広く波及していることがわかった。
そして来年の賃上げも連合が「5%以上」とすることを決定し、経営側の経団連も理解を示すなど、政府・経済界も大幅な賃上げで足並みを揃えている。
すでに経済同友会の新浪剛史代表幹事が社長を務めるサントリーホールディングスは来年の春闘で定期昇給分を含む7%の賃上げをめざすことを表明している。
また、家電販売大手のビックカメラは社員約4600人を対象に月2万~3万円のベアを実施する方針であり、住友生命保険も営業職員約3万人を対象に平均7%以上の賃上げを行うことを決めている。
昨年に引き続き、誰もが来年4月からの給与アップを期待したくなる。
しかし、残念ながら同じ会社に勤めていれば誰もが上がるわけではない。平均3万円、あるいは平均5%アップといっても、あくまで賃上げの原資を社員数で除したものにすぎない。原資をどの層にどれぐらい配分するかは会社(あるいは労使)が決めている。そしてベースアップ分を全社員一律に配分する企業はそれほど多くはないのが実態だ。
経団連の「2021年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」では、ベースアップを実施した企業の具体的な配分方法を聞いている(複数回答)。
それによると、「一律定額配分」の企業が35.1%、「一律定率配分」企業は10.4%であり、全社員に平等に配分している企業はそれほど多くはない。
では、どのように配分しているのか。
「業績・成果などに応じた査定配分」が26.1%となっている。つまり、ベースアップといっても一律に昇給させるのではなく、個人の成果の達成度に応じた評価昇給の企業の一定数を占めている。成果を出せなければベースアップの恩恵を受けられない社員もいるということだ。
さらに興味深いのは「若年層(30歳程度まで)へ重点配分」の企業が18.7%。「中堅層(30~45歳程度)へ重点配分」が9.7%となっていることだ。賃上げの原資を若い層に多く配分していることがわかる。
■しわ寄せをくっているのは40、50代…物価を下回る賃金
一方、「ベテラン層(45歳程度以上)へ重点配分」する企業は2.2%にすぎない。つまり、賃上げの恩恵を多く受けているのは若手社員層であり、逆に中高年社員は雀の涙程度しか受け取っていないということもできる。
なぜ若手社員に多く配分するのか。建設関連会社の人事担当者はこう語る。
「人手不足が深刻化し、人材の獲得競争が激化している。新卒に限らず、優秀な中途人材を確保するには給与をアップしなければ誰も見向いてくれない。また、若年層の賃金を上げなければ今いる社員も離職してしまう可能性もある。若手に多く配分したいというのはどこの企業も同じだろう」
それを象徴するのが大卒初任給の高騰だ。今年は電機大手やメガバンクをはじめあらゆる産業で初任給引き上げが相次ぎ、大卒初任給は一気に25万円が相場となりつつある。
さらにゼネコンの鹿島は24年4月に入社する総合職の社員の大卒初任給を3万円引き上げ、28万円にすると公表している。
製造業の産業別労働組合の幹部は「3年ぐらい前までは大手企業を含めて初任給の水準はほぼ同じだった。しかし、22年の春闘の頃から初任給を引き上げる企業が出始め、23年は一挙に2万円、3万円を引き上げるなど初任給競争が激化し、初任給インフレの様相を呈している」と、呆れる。
実際に人事院の調査(令和5年職種別民間給与実態調査)によると、今年4月に入社した東京23区内の大学卒の初任給は事務系が約22万2000円。前年より3.0%もアップしている。ただし、初任給のみを引き上げるだけではすまない。バランスをとるために、少なくともその上に在籍している20代後半までの社員の賃金の補正も必要になり、30歳前後の社員の賃金も自動的に引き上げられることになる。
その分のしわ寄せを受けるのが前述の45歳以上の中高年社員だ。45歳といえば、就学児童を抱え、教育費などまだまだ生活費にもお金がかかる。賃上げの配分が雀の涙程度では、今の物価高では生活も楽ではない。その実態について連合総研(第46回勤労者短観調査結果、10月31日)が調査している。
今年の賃金の増加幅が物価上昇幅より大きいと回答した割合は6.9%だった。これは厚労省の毎月勤労統計調査の物価を加味した実質賃金(10月)が19カ月マイナスであることを考えても当然の結果だろう。ところが世代別にみると大きな違いがある。
20代は賃金の増加幅が物価上昇幅より大きい、つまり物価を上回る賃金をもらった人の割合は10.9%、賃金と物価の上昇幅が同程度の人が22.1%となっている。少なくとも物価に見合う賃金を受け取った人は33%もいる。
それに対して40代は物価を上回る賃金をもらった人は6.0%、同程度の人が15.9%。計21.9%にとどまる。
50代は物価を上回った人はわずかに2.8%、同程度が12.6%。計15.4%にすぎない。
そして40代の61.7%、50代の69.7%が、物価を下回る賃金しかもらえなかったと回答している。
今年の賃金が大幅にアップしたとはいっても、中高年社員はわずかしか上がらず、しかも物価には追いつかず、厳しい生活を強いられている。
しかもこうした傾向は今に始まったものではない。
■40~50代賃金はかつては20~24歳の2倍も今は1.5倍
社員の賃金は2000年以降、下降傾向にある。年齢階級による賃金カーブ(所定内給与)は20~24歳を100とした場合、45~49歳は1995年に191.0だったが、2022年は159.8にまで下がっている。
50~54歳は1995年に194.4と、約2倍だったが、2022年は166.9となっている(労働政策研究・研修機構調査)。
このまま推移すれば、中高年の賃金はいずれ20~24歳の1.5倍程度しかもらえなくなる日も近いだろう。これは全体の数値であるが、同じような傾向がどこの会社でも起きているだろう。
仮に24歳の月給が25万円であれば、1.5倍なら中高年は37万5000円になる。この給与で家族を養うことは難しくなる。
実は少子化の原因の大きな一つには中高年の賃金低下にもあると筆者は考えている。結婚適齢期の30代にとって15年後、20年後のときに自分はどのような職業人生を歩んでいるかを想像すると、モデルとなるのが45歳以上の会社の先輩だ。
先輩の給与が上がらない現実を目の当たりにしたとき、子どもが2人ほしいが、大学に行かせるのは無理だと直感的にわかる。持つとしてもせいぜい1人だろうと考えても不思議ではない。中高年の賃金の低迷は従来のライフスタイルの変更を迫られる。
少子化対策を考えるなら、子ども手当の増額もよいが、下がり続ける中高年の賃金のアップを期待したい。
———-
人事ジャーナリスト
1958年、鹿児島県生まれ。明治大学卒。月刊誌、週刊誌記者などを経て、独立。経営、人事、雇用、賃金、年金問題を中心テーマとして活躍。著書に『人事部はここを見ている!』など。
———-

<このニュースへのネットの反応>