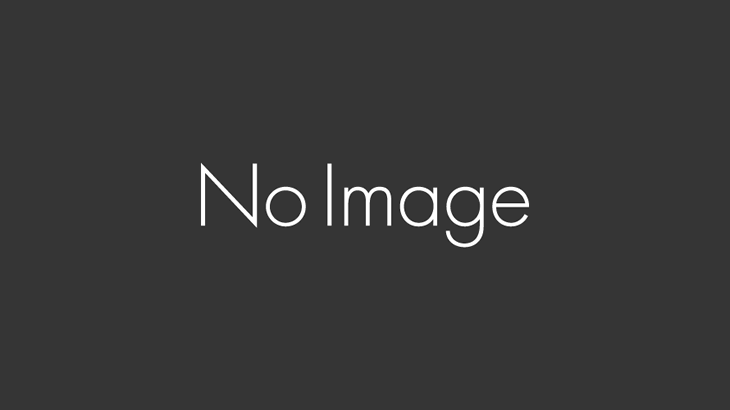あわせて読みたい
なぜ欧米では「高齢者の暴走事故」が話題にならないのか…日本特有の「薬漬け医療」に潜む巨大リスク
※本稿は、和田秀樹『医者という病』(扶桑社新書)の一部を再編集したものです。
■薬を大量に飲めば毒になる
日本の医者は「専門医」ばかりで「総合診療医」がほとんどいないため、大量の薬を飲んでいる高齢の方は少なくないでしょう。しかし、高齢になると薬の過剰摂取は、より一層慎重になるべきだと思います。
それは、若い頃に比べ、薬の効果が薄れていくのに時間がかかるからです。薬を飲むとだいたい15~30分後に、血液中の薬の濃度が最も高くなります。その後、薬の成分を肝臓の分解や腎臓の排泄を経て、8時間から半日ほど経過すると血中濃度は半分くらいになります。これを「半減期」と呼びます。
多くの方は薬をもらったら、一日に2、3回飲むように指示されると思いますが、これは血中濃度が半分くらいになった半減期に次の薬を飲むことで、血中濃度を一定に保つ狙いがあるからです。
若い人ならばこのサイクルで薬を飲むのは問題ないのですが、高齢になってくると、そうはいきません。
年齢が上がるにつれて、体力の衰えと同様に腎臓の消化器の働きも衰えて、薬が体外へ排泄される時間も当然延びていきます。年をとってくると肝臓の機能が落ちるので薬を分解する時間が長くかかります。
若い頃は半減期が6時間だった薬でも、高齢になると半減期に至るまで12時間以上かかるなんてことはざらにあります。その場合は、若い人と同じように薬を飲んでいては、体に薬が蓄積することになるので、量や飲むサイクルを調整する必要があります。
■薬漬けで体調を崩す高齢者
適量ならば体に良い効果をもたらす薬も、上手に分解されなかったり体外に排泄できず過剰に残ってしまえば、毒と同じになるでしょう。人によっては意識障害や内臓の機能障害、寝たきりや認知症などの病気を引き起こす可能性もあります。
高齢者を専門とする医師にとって、こうした薬の調整は常識です。
しかし、日本の大半の医療関係者は、「成人」とみなした患者さんならば、180センチ90キロの20代男性と、140センチで40キロの90代女性に同じ量の薬を処方するのが一般的なのです。これでは、高齢者が薬漬けになって、体調を崩すのも当然のことでしょう。
当たり前のことですが、高齢になるほど体にはガタがきます。ある程度の不調とは付き合っていくのが当たり前なのに、日本では体の悪いところすべてに薬を出して治そうとします。
当然、お金がかかりますし、常時五種類以上の薬を飲んでいれば副作用が急激に増えるので体に悪い。薬によって特定の不具合は解消されるかもしれませんが、そこで得られるメリットよりもデメリットのほうが多くなる可能性が高いのです。
■「この薬を飲めば脳卒中になりませんよ」医者がつく典型的なウソ
みなさんもご存じの通り、子供が飲む薬の量は大人と違います。体格や体の機能が異なる大人と同じ量の薬を飲むと、副作用が大きくなってしまうからです。これは、高齢者も同様に考えるべきなのです。
本来ならば、日本人の高齢者を対象に大規模調査をして、それぞれの年代や体格の人に本当に必要な薬の量を調べ、適正量の薬を処方するように指導するべきなのに、こうした動きをする医療関係者はほとんど見当たりません。
また、すべての薬は、基本的には延命治療の一環です。なぜなら、死ぬ確率をゼロにする薬は、世界中どこにもないからです。しかも、治療をしても、本当に延命できるかどうかの日本でのエビデンスはありません。医療とは万能ではなく、あくまで不確かなものに頼っているに過ぎないのです。
「この薬を飲めば脳卒中になりませんよ」「この薬を飲まないと、確実に心筋梗塞になります」というのは、医者がつく典型的な嘘です。
今一度、「薬を飲む害」について考えていただきたいものです。
■なぜ欧米では「高齢者の暴走事故」が話題にならないのか
日本は高齢者に対する医療が非常に手厚い。ただ、多くの医者が勉強をせず、高齢者の症状や治療法について知らないため、私から見ると間違った方向の予防投薬をし続け、高齢者の健康を大きく害しているのが現状です。
血圧や血糖値を薬剤で管理しているせいで、さまざまな弊害が高齢者に生まれているのをご存じでしょうか。
血圧や血糖値やナトリウム値を下げすぎると意識障害が起きます。そのほかさまざまな薬の副作用で意識障害が起きるのです。これは体が起きているのに頭が寝ぼけているような状態です。
昨今、高齢者ドライバーの暴走事故が取りざたされていますが、こうした事故が話題になっているのは、世界中で日本だけです。欧米では高齢者の暴走事故は、ほとんど話題になりません。
大半の高齢者の暴走事故は、普段真面目に安全運転している人が、その日に限ってものすごいスピードを出し、信号無視を2つくらいして人を殺してしまうようなものが報じられています。
多くの医者を含めた識者といわれる人たちは「高齢による運転能力の低下だ」と結論付けていますが、高齢者専門の医者からすれば、明らかに意識障害によって引き起こされたのだろうと推測できます。高齢者の臨床に携わり、日頃から高齢者の意識障害を見たことがある人ならば、すぐに想像できることです。
■日本の医者は「薬の副作用」を軽視している
実際、入院患者の10~30%にこの手の意識障害が起こり、高齢者はもっと多いとされています。もちろん家にいる時にも起こりますから、車の運転中に起きたとしても不思議はありません。
しかし、高齢者医療の現場を知らない上にマスコミとテレビに出してもらいたい多くの医者は、それを年齢のせいと片付け、せん妄を疑いません。しっかりと原因を解明しないままに、ひたすら「高齢者の暴走事故が起こるから、シニア世代になったら免許を取り上げろ」とだけ叫び続ける。これも由々しき事態です。
先に挙げた例を見てもわかるように、多くの日本の医者は薬の副作用についてあまり真剣に考えていません。その大きな理由として考えられるのは、薬の副作用によって患者さんが亡くなることがあっても、医者が罪に問われないという法体制にあるでしょう。
もしも患者さんに副作用が出て何かあっても、製薬会社が罪に問われるだけ。実際に薬を投与した医者たちは「副作用について知らなかったのだからしかたない」「ガイドラインに従って処方しただけ」と言い逃れることができます。
■アメリカの医者が薬の数を減らそうとする理由
自分が処方した薬で患者さんに何かあっても、自分は痛くもかゆくもない。ですから、日本の医者たちのほとんどは、薬の副作用に関する知識を蓄えようとしないのです。これは決して世界のスタンダードではありません。
アメリカの医者は、副作用を非常に気にします。仮に副作用が出て、患者さんの体に危険が及んだ場合、製薬会社のみならず、処方した医者も「副作用に対する認識が甘かった」として訴えられるからです。
ですから、アメリカの医者たちは、製薬会社の営業担当者であるMRから新しい薬の宣伝を受けた際に、真っ先に副作用についてあれこれ質問します。実際に私もアメリカに留学中、何度もそのシーンを見る機会がありました。
日本の医者がMRと交わす会話といえば、ゴルフや会食の約束がメインで、薬について質問するとしても、その薬の良いところばかり……というのが通常だったため、アメリカの医者たちの副作用に対する意識の高さに驚愕(きょうがく)したのを覚えています。
アメリカの医者は訴えられるのが怖いので、少なくとも副作用を勉強します。さらに、何種類も薬を出すと何かしらの副作用が出ることはわかっていますから、できるだけ処方する薬の数を少なくしようとします。エビデンスのない薬を何種類も処方するなんてことは、間違ってもしません。
■薬害で医者は訴えられない
日本の有名な薬害訴訟でも、医者が責任を問われる事態は見られません。1960年代には、神経障害が一生残る病気・スモンを発症してしまうキノホルムという整腸剤を処方した医者や、サリドマイドという肢体の不自由な子供が産まれてしまう副作用がある鎮静薬を出した医者も、訴えられることはありませんでした。
そのほか1970年代にも、抗マラリア剤のクロロキンを用いたことで、多くの患者さんが網膜症を患う事件がありましたが、処方した内科医は訴えられていません。つまり、日本で起こったほとんどの薬害で、製薬会社は訴えられても、薬を出した内科医は訴えられていません。
■過剰な薬剤費が社会保険料増大の原因になっている
薬を減らすことは、社会にも良い効果をもたらします。
昨今、社会保険料の負担額が大きな話題になっています。当然のことですが、高齢者が増えれば、それだけ医療費も増大します。それゆえ、「老い先短い高齢者にばかりお金を使っているのは無駄ではないのか」「高齢者のための医療費負担によって、若者世代の税負担が増えている」などという批判の声が上がり、高齢者医療に対して見直すべきではないかという風潮もあります。
高齢者の医療費が増えてしまう大きな要因は、過剰な薬剤費です。日本の医療費の約4割が薬剤費だといわれていますが、高齢者はもっと高い割合なのではないでしょうか。そして、世界的にも薬剤費の割合が非常に高いのです。
近年は医療業界の人手不足によって、看護師の数も減っているため、人を増やす代わりに薬を増やしているという実情もあります。専門分化型の医療をやめて総合診療に切り替えれば、いま15種類ほど飲んでいる薬を3、4種類に抑えられます。そうすれば、薬代は減るし、体への負担が減って健康になるので、より多くの方が医者いらずで長生きできることでしょう。
■手あたり次第に薬を出す医者を放置していいのか
これだけ悪い状況が重なっているのに、将来の病気予防と称して現在症状のない患者さんに、医者が薬を出しすぎる状態が改善されないのは、指導官庁としての機能を果たしていない厚生労働省の責任です。
アメリカの例ばかりで恐縮ですが、同国では、医療費は原則的に保険会社が出します。
保険会社側は、赤字になっては困るので、きちんとしたエビデンスのない薬を出すような医療機関に対しては、「その薬にはエビデンスがないのでその薬についてはもうお金は出さない」「複数の薬の相互作用のエビデンスがないので二剤の併用にはお金が出せない」などと指導します。
このエビデンスというのは、血圧を下げるだけではダメで、その薬を飲むことで5年後の脳卒中や死亡率を下げるという統計上の根拠のことです。
ところが、日本の場合は、公的な健康保険の審査がゆるいので、事実上のノーチェック。本来なら保険機構がエビデンスのない薬には金を出さないスタンスを取るべきですが、日本にはそれがありません。結果、無駄に薬が使われ続け、国民の医療費負担が増えていくばかりです。だからこそ、国会などで審議されることもなく、厚生労働省の省令によっていつの間にか給料から引かれている社会保険料の額が増えるという不可解な事態が起こっているのです。
余分な薬剤費を払うよりは、介護費用やリハビリ費用に回したほうが、高齢者のQOLは上がるはずですし、ケアする側の負担も軽減できるはずです。
問題点は、医者たちが手あたり次第に薬を処方するので、本当に必要な薬剤費がいくらなのかがわからなくなっていることです。現在、薬剤費は医療費の約4割を占めていますが、現状を放置していたら、比率が上がる可能性が極めて高い。今後数十年間にわたって、日本社会にはびこる大きな病巣になってしまうことでしょう。
———-
精神科医
1960年、大阪市生まれ。精神科医。東京大学医学部卒。ルネクリニック東京院院長、一橋大学経済学部・東京医科歯科大学非常勤講師。2022年3月発売の『80歳の壁』が2022年トーハン・日販年間総合ベストセラー1位に。メルマガ 和田秀樹の「テレビでもラジオでも言えないわたしの本音」
———-

|
<このニュースへのネットの反応>