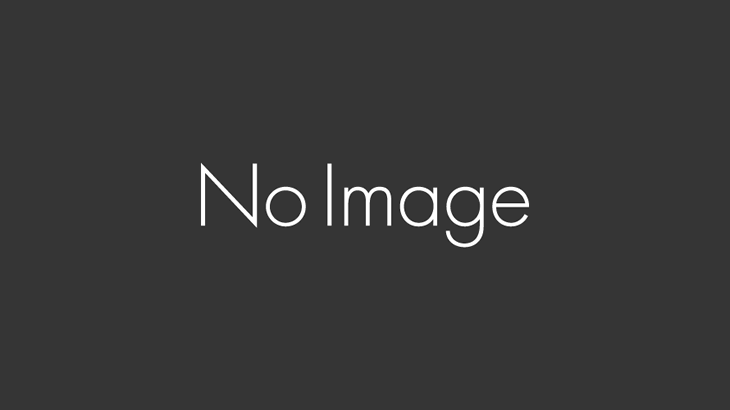あわせて読みたい
「一体何を考えているのか」と思わず呆れる、生活保護受給者のパチンコに対する権利主張に批判が集まる
「生活保護でもパチンコで遊ぶ権利はある」こうした主張に多くのサラリーマンが不快感を抱く根本原因 | ニコニコニュース
|
|
【生活保護】2023年10月から適用される新しい生活保護費について解説 – YouTube
(出典 Youtube) |
※本稿は、平川克美『「答えは出さない」という見識』(夜間飛行)の一部を再編集したものです。
■周囲から見ると不合理な特権を得るための努力
(前回からつづく)
ちょっと蛇足なのですが、関係のあるお話をします。
たとえば、おいしい行列のできる料理屋があるとします。そこに入るには、30分から1時間、待たなくてはなりません。けれど、店主と仲良くなっていれば、特別扱いをしてもらい、フリーパスで列に並ばずに料理を食することができるかもしれません。
そう考えて、そのために日頃から付け届けをしたり、特別な関係を作るための努力をする人が、この世の中には思った以上にたくさんいるのです。もちろん、これは自分が特別扱いされるために、努力をする人間がいることの譬え話です。
さて、列に並ばずに店に入れるような特権的ポジションを得るために努力する。この努力たるや、列に並んで30分から1時間待つのと比べたら、ずっと大きなエネルギーが必要だったりします。なのに、なぜかそうするんですね。特権を獲得するために合理的な行動をしていると当人は考えているのでしょうが、周囲から見ると極めて不合理なことをしているとしか思えない。
■列があったら並んだほうがいい
たとえば、詐欺師は自分の詐欺を完全なものにするために、できうるかぎりの努力をします。その努力をまっとうなことに使えば必ず成功するくらいの労力を注ぐ。でも、そうしたまっとうな道は選ばず、詐欺を選択する。なぜなら、「詐欺をしたほうが利得が大きい」という考え方にとらわれてしまっているからです。そういう人間が、一定程度、いやそれ以上にいるのです。まあ、詐欺を一種の芸術であり、完璧な詐欺に生きがいを感じるなんていう人もいるでしょうが、それは別の話です。
私の場合は、たとえば列があったらそこに並ぶでしょう。人には与えられた条件というものがあって、それが公平性を担保しているならば粛々と受け入れるべきだと考えるからです。並びたくなければ、食べないまでです。
何らかの特権を使って、人よりも先に店に入って、おいしいはずの料理を食べても、どこか無味乾燥なものになってしまうような気がします。どんな見事な料理であっても、自分が特権を使ってそれにありついているという意識になれば、本当においしく感じるかどうかは疑問だし、あまり楽しいことではないような気もします。
ここで、その人を満足させるのは特権意識だけです。この特権意識たるや、その人間のさもしさを浮き彫りにしているだけです。貧乏人のひがみかもしれませんが、貧乏人には貧乏人だけが味わうことのできる喜びというものがあると信じたいですね。
■日本人の労働観は1980年代を境に変化した
私は、自分が元気に充実して働いていられて、誰かに休みを譲れるのであれば、譲ってあげてもいい、と思います。きれいごとだと言われるかもしれませんが、零細企業の社長しかやったことがなく、有給などとは無縁の、休みなしの生活を続けてきたのですから、これくらいは言わせていただいてもいいでしょう。
「有給休暇とは、働くことをより楽しく感じることができるようにリフレッシュするためにある」のであって、有給取得のために働いているわけではないからです。なのに、労働と休暇における本末の逆転現象が、このところ顕著になっているように感じます。
あなたが指摘した「労働者の権利はすべて使い切る」という発想は、日本人全体の労働観が1980年代頃を境にして少しずつ変化した結果なのです。80年代を境にして、日本人全体が、自己意識を、生産者から消費者へと軸足を移した。意識のうえで、多くの労働者が、自分を生産者ではなく消費者として規定するようになったということです。
■労働は「消費のための手段」となった
それ以前の日本人は生産者でした。多くの人々が第一次産業、第二次産業の生産業に従事していましたから、消費というのは、自分が生産し、生産した幾分かを消費で買い戻すという、ささやかな楽しみだったのです。
それが、あるところから「消費をするために働く」ようになった。つまり、働くことが、消費をするための作業になったのです。それ以前は、働くこと自体が目的でした。なぜなら、それ以外の働き方をしようにも、できなかったからです。月曜日から土曜日まで働きづめに働いて、日曜日は疲れ切った身体を休める。生きるとは、働くことだったわけです。
「労働が消費のための手段となった」現象を、社会学では「消費化」と定義していますが、これ自体は悪いことではありません。なぜなら、人々がつらい労働から解放されるプロセスとも言えるからです。しかし、よい面が生まれれば必ず悪い面も出てくるものです。
働くことが手段化したことにより、働く“喜び”がなくなってしまいました。また、仕事の工夫もしなくなり、何よりも、労働に対する倫理観がなくなりました。なるべく努力をしないで、最大の果実を得る(=存分に消費する)ことが人々の目的となったのです。
もちろんこれは、極端な言い方をしています。しかし概ね、このような変化が起きてきたということは、言ってよいと思います。
■「消費化」によって起きた本末転倒
そして、この消費化がどんどん徹底されていくと、さまざまなシーンで本末が転倒していくことになります。たとえば、健康を追い求めて、禁酒・禁煙、玄米食で毎日ランニングを欠かさなかった人がけっこう早死にしたりするのは、人生の目的が「楽しく生きること」よりも、「苦労して健康を獲得すること」になってしまい、本来必要な、栄養や快楽を制限してしまったことによるのかもしれません。
いわゆる「健康という病」ですね。健康は目的ではありません。「健康な体を持っていれば、楽しく生きていける」というのが本分ですね。「楽しく生きていく」ことが目的なのに、いつのまにか健康が目的になってしまっている。このように、良きことであっても、それに執着してしまえば、本末が容易に転倒してしまいます。原理主義とは、そこに陥った状態です。
「与えられた権利はめいっぱい使わなくてはならない」という考えにも、“消費者原理主義”の兆候がうかがえます。仕事と人生を楽しむために有給を取得するはずが、消費者マインドが徹底してしまうと、有給を“消費する”ことに気持ちがいき過ぎ、そのために努力するという事態に陥るわけです。
■学生はお客さんで、教育内容はソフト商品
私は大学で教えていましたが、学期の始まる前に、大学側からシラバスを書くように指示されます。シラバスとは、一回ごとの授業の内容を書き記したもので、大学側はその後、学生に対してシラバス通りに授業がなされたかどうかを確認します。私は、この傾向は、教育の本義とかけ離れたものだと思っています。
「教育の本義とは何か」という問いにお答えするのは大変に難しく、今回のテーマから外れてしまうのでここでは詳しく説明しませんが、教育の本義が「何でないか」ということは明言できます。
教育の本義は、サービスではありません。ビジネスにおける商品交換ではないということです。
しかるに、今日の大学は、教育をサービスの一環として考えているふしがあります。
学生はお客さんで、教育内容はソフト商品です。ですから、シラバスは、商品のスペック(仕様書)というわけです。
■大学にまで蔓延する消費者マインド
学生は“授業という商品”を買い、教師はそれを買ってもらう立場になっている。
私は、教育にスペックなどは、本当はいらないし、むしろ害になると思っています。だから、シラバスもいらない。ある程度のガイドラインがあればいい。
だけど、生徒は消費者マインドになっており、大学はCS(カスタマー・サティスファクション=顧客満足)を満たすための授業を商品として提供する機関になっている。
大学という、商品交換の世界からもっとも遠い場所にまで、消費者マインドが瀰漫(びまん)してきているのですね。
消費者マインドは、非常に強い強度を持って現実に編成されていることがわかります。それはもう、地球上のすべてを覆いつくすような勢いです。それは、なぜなのでしょうか?
■世界は等価交換と贈与交換の原理で動いている
この原理は、等価交換による貨幣経済の仕組みがもとになっていると私は思います。等価交換とは、「自分が損をしないように相手と交換する」ということです。
けれど、よく考えてみてください。
この世の中に、実は等価交換は思ったほど多くありません。多くのことは、等価交換ではなく、贈与交換によって成り立っています。たとえば、家族間でのお金の貸し借りに利息はありません。そこには通常の等価交換とは違う、贈与交換の原理が働いているのです。
親が子どもを育てることは無償の贈与であり、子どもが親の面倒を看るのも贈与に対する返礼である。こうして、いわゆる贈与に対する返礼という形の交換原理と、貨幣交換という原理がこの世の中に共存しています。
そして、交換のこの二つの原理によって世界は動いている。
しかし、消費者マインドが進んでいくと、貨幣交換(=等価交換)しか見えなくなり、贈与交換が隠蔽(いんぺい)されてしまうという現象が起きてくる。
■生活保護受給者のギャンブルに対する批判の根底
よく、生活保護受給者に対して、「パチンコや競馬をするなんて、けしからん」と、与党の政治家が言いますよね。行政側がそうした、生活保護受給者は世間に頭を下げながら生きていくべきだといった姿勢で受給者に対しているということが、何度か問題になっています。
罵声を浴びせる側は、「俺たちが汗水たらして働いて得た給料から税金が引かれ、それが生活保護費の元手になっているのだから、もらっている人間が楽しんではいかん」と主張します。この考え方に対して、「それは間違っている」と納得させるのはなかなか難しいのです。
実際に「生活保護受給者にもパチンコや競馬で遊ぶ権利がある」という主張には、多くのバッシングが起こりました。そうした批判をした人々の多くは、普通のサラリーマンやビジネスマンでした。
彼らの意識には、「生活保護受給者は努力が足りないのだ」という考えが根底にあるのでしょう。「働かないでお金をもらって遊んでいるとは何事か!」という考えは、人間には根強くあるのです。
■働かないで商品を買うのは等価交換の原理に反する
では、彼らが依拠している原理とは何なのでしょう。
私は、それこそ等価交換の原理であり、その原理が生み出した消費者マインドだと考えています。
彼らは、自分の労働を売って、賃金を買い取り、その賃金で自分の労働力の成果である商品を買い戻すというサイクルのなかに生きています。そして、隣に働かないで商品を買っている人がいれば、激しい不公正感を抱くのです。
これは、等価交換の原理に反していると。不平等ではないかと。
もし、そこで贈与交換的な価値観を思い出す精神的な余裕があれば、「この人たちが今、仕事ができない・収入がないのは、社会の責任でもあるわけだから、社会から贈与を受けてしかるべきだ」という考え方が生まれるはずです。しかし、そこへはなかなかたどりつかないのが現実です。
■差別感情は同じような貧乏人同士の間で顕在化する
実際に、今のような就職難・低賃金の時代には、汗水たらして働いて得た賃金で、かすかすの生活を維持するのが精一杯という賃労働者がたくさんいるわけで、場合によっては生活保護支給額を下回る賃金で働いている方々も多いと聞きます。
これは非常に切実な問題ですね。みんな、金持ちや貧乏な人々、どちらに対しても公平性を求めます。けれど、どちらかと言うと、金持ちが税金などで優遇されることに対してはそれほど不公平感を持ちません。勝ち組と言われる成功者に対しては「自分が努力して金持ちになったのだから」と認め、身近なところに不平等感を感じてしまう。負け犬と呼ばれたくない。今の境遇は自己責任なのだから、しょうがない、というふうに。
差別感情というのは、大金持ちと貧乏人というような絶対的な差異のなかではほとんど顕在化しません。お互いに無関心にならざるを得ない。しかし、同じような貧乏人同士の間にある小さな差異には敏感になってしまうのです。
■エコノミークラスの健常者が抱く嫉妬心
人は差別感情からなかなか自由になることができません。
列に並ばないで、スーッと自分だけ先に店に招き入れてもらえるような特権的な立場が欲しいというのも同根の感情によるものでしょう。
こうした感情は、誰にでもあります。
現実にも、差別は社会のあらゆるところで組織化され、構造化されています。飛行機の搭乗のときにはファーストクラスとハンディキャッパーの人々が先に呼ばれて搭乗します。その両方の人たちに対して、エコノミークラスの健常者は少なからず嫉妬心を抱きます。
ただ、嫉妬心こそ抱くものの、それが怒りとして表明されるまでには至りません。もしもエコノミークラスの客同士の間で、一方が優遇されたりすれば、不平等感を募らせ、もっと激しい怒りが湧いてくるかもしれませんね。
以前、「差別感情は誰にでもある。なのに、それをあたかもないかのようにきれいごとを言っているヤツがたくさんいる」と公然と主張した政治家がいました。
「そういうのは、やめろ。きれいごとは言うな」と彼は言う。「現実には差別は厳然とあり、世の中は不平等で冷徹なのだ」と。それは、ある意味では、現実を言い当てているのかもしれません。
■贈与交換は人類が必要とし、使い続けてきた原理
でも、それは現実のいち側面かもしれないけれど、すべてではないのです。東日本大震災のあとに人々が助け合い、今も都会の混雑するホームにおいても困っている人がいたら、人々が優しい態度で手助けすることがある。そういう、もうひとつの現実がある。そうした贈与交換の原理が、等価交換の原理の猖獗(しょうけつ)の下では、隠蔽されてしまうのです。
社会が、等価交換の原理に覆われてくると、贈与交換の原理が隠蔽されてゆく。しかし、本当は、この二つの原理が私たちの世界には存在しており、それらが補い合って社会の秩序を作っています。
贈与交換なんていうと「きれいごと」に聞こえるかもしれませんが、実は、人類がこれまでの歴史のなかで生き延びていくために必要とし、使い続けてきた原理です。それがなければ、とっくに人類は死滅していたでしょう。
■自己欺瞞であっても「きれいごと」を言うことの意味
「きれいごとを言うのは、他者からよく思われたいという自尊感情の現れであり、自己欺瞞(ぎまん)だ。自分は他人からどう思われようとかまわないから、きれいごとではなく、自分の言いたいことを言う」というようなことを言うコメンテーターやネット上の有名人がいます。でも、それって「他者が自分をどう思うかを計算している」という点では、同じじゃないかと私は思います。
少しでも、自分たちが生きている社会を生きやすい、風通しのよいものにするためには、自己欺瞞であっても「きれいごと」を言って自分のエゴを抑え込むことが必要であり、そのようにして少しずつ、「きれいごと」が不自然ではない社会が形成されていけば、それに越したことはない。私はそう考えます。
自己欺瞞であることを知っているものが発する「きれいごと」には、意味があるということです。
———-
実業家、文筆家
1950年東京生まれ。早稲田大学理工学部機械工学科卒業後、渋谷区道玄坂に翻訳を主業務とするアーバン・トランスレーションを設立。1999年シリコンバレーのBusiness Cafe Inc.の設立に参加。2014年、東京・荏原中延に古き良き喫茶店「隣町珈琲」を開店し、店主となる。現代企業論を独学で研究し、立教大学特任教授、客員教授、早稲田大学講師を歴任。著書に『小商いのすすめ』(ミシマ社)、『俺に似たひと』(医学書院)、『グローバリズムという病』(東洋経済新報社)、『路地裏の資本主義』(KADOKAWA)、『移行期的混乱』(筑摩書房)、『言葉が鍛えられる場所』(大和書房)、『21世紀の楕円幻想論 その日暮らしの哲学』(ミシマ社)、『共有地をつくる わたしの「実践私有批判」』(ミシマ社)、『復路の哲学 されど、語るに足る人生』(夜間飛行)などがある。
———-