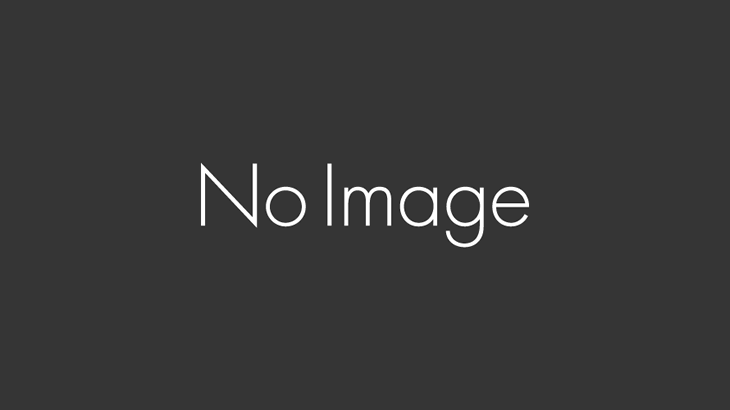あわせて読みたい
なぜ多くの日本人は広末涼子に怒るのか…「中年夫婦の半数以上はセックスレス」という不都合な真実
なぜ多くの日本人は広末涼子に怒るのか…「中年夫婦の半数以上はセックスレス」という不都合な真実
|
■強まるばかりの不倫バッシング
女優・広末涼子氏の「W不倫」は、通常のスキャンダルにとどまっていない。
みずからの無期限謹慎、お相手のシェフ・鳥羽周作氏の謝罪、「愛の交換日記」の公開、さらには夫、キャンドル・ジュン氏の涙の記者会見まで、つぎつぎに更新され、国民的な関心の的でありつづけている。
今回の事態をめぐって、不倫そのものの是非よりも、ここ数年、ますます強まるばかりの不倫バッシングの理由が注目に値するのではないか。
■不倫をネタとして楽しむ社会
不倫は良いのか悪いのか。
古今東西、この話ほど結論が出ないゆえに、多くの人たちの興味をそそる話題はない。
何よりも、わたしの書いているこの文章も「一億総不倫評論家時代」ともいうべき流行に乗って、ご依頼をいただいたものである。
ご多分に漏れず、いや、それ以上に、わたしは昔から不倫ネタを愛しており、小学生のころからワイドショーを凝視してきた。
不倫を擁護する側も、口を極めて罵る人も、あるいは、わたしのように高みの見物を決め込もうとする立場も、あらゆる見方をふくめて、不倫をネタにしているところに変わりはない。
今回のタイトルである「不倫バッシングの理由」すら、ネタとしてさんざん消費され尽くしてきた。
不倫にまったく関心がない、と断言できる強者は、どれだけいるだろうか。
■「不倫」は、昭和末期のことば
とはいえ、「不倫」ということば自体は、そんなに古いものではない。
その歴史については、江戸期についての斬新かつ懇切な多くの研究書で知られる氏家幹人氏の『不義密通』〔講談社選書メチエ(1996年)、→洋泉社MC新書(2007年)〕で明らかにしている。
氏家氏によれば、不倫=人妻の姦通(夫以外の男性と性関係を持つこと)、つまり、今の意味で使われるようになったのは、40年ほど前、1980年代前半である。
日本語辞典『広辞苑』には、1955年の第一版以来、不倫は「人倫にはずれること。人道にそむくこと」としか記されていなかった。
1983年11月に出た『広辞苑』第三版にはじめて「不倫の愛」という用例が加わる。
理由は定かではないものの、氏家氏の指摘するように、この同じ年にテレビドラマ「金曜日の妻たちへ」(略称は「金妻(きんつま)」)(TBS、脚本・鎌田敏夫)が始まる。
氏家氏の本を受け継ぐかたちで、文芸評論家として日本の恋愛史に通じる小谷野敦氏が調べたように、このころ、つまり、1983年ごろから週刊誌の見出しにも「不倫」が増えていく(小谷野敦『性と愛の日本語講座』ちくま新書、2003年)。
『日本国語大辞典』にも引かれているように、1903年には国木田独歩、その少し後(1909年完結)には田山花袋という2人の明治の文豪が「不倫」を、既婚者による配偶者以外とのセックスとして使っている。
まったく新しいわけではないものの、今と同じ使われ方は、そう古いわけではない。重要なのは、「不倫」が、それ以前の表現と比べてネガティブな印象をまとっているところにある。
■40年間で「不倫=悪」が定着した
昭和のあいだ、しばしば使われていたのは「浮気」や「よろめき」だった。
「金妻」よりも6年前、1977年に同じくTBSで放送された「岸辺のアルバム」の第1話には「人妻の70%は浮気をしているといいます」という謎の電話がかかってくる。
あるいは、三島由紀夫には『美徳のよろめき』(1957年)と題した小説はベストセラーとなり、「よろめき」は流行語になった。
「浮気」は文字通り、「浮ついた気持ちであって、本気ではない」、とか、「よろめき」は、「ふらついてしまっただけ」、といったかたちで、どちらも、一時の気の迷いであるとの言い訳につなげられる。
これに対して「不倫」は、より批判のニュアンスが強い。
不倫は、「人倫」=「人の道」に反しているし、「破倫」や「乱倫」にも通じる、非道徳で、人の気持ちを踏みにじっている。
このことばが定着してからの40年間は、婚姻関係以外の関係について、マイナス面ばかりが強調されてきた。その果てに、昨今の不倫バッシングがある。
■「瀬戸内寂聴」は、もう出てこない
今回の「W不倫」に注目が集まるのと時を同じくして、ラジオプロデューサーの延江浩氏による小説『J』(幻冬舎)が出版された。
同作は、2年前に99歳で死んだ作家の瀬戸内寂聴が、48歳年下の妻子ある男性と4年にわたって不倫関係にあった、その日々を、あけすけな性描写とともにつづっている。
「W不倫」、それも、広末氏と鳥羽氏による「交換日記」の文面をことこまかに暴露した『週刊文春』は、同じ号で、『J』の中身や背景を解説している。
日本国憲法第21条で保障されている「通信の秘密」を侵しているのではないか、との非難の声が日に日に高まる記事を載せながら、『J』についての記事を、つぎのように結んでいる。
“男女の性愛を余すところなく描いた瀬戸内寂聴。死後も、愛と性にまつわる話題で我々を驚かせるのも、彼女の面目躍如である。”
広末氏が、将来その生涯を終えたあとに、こうした評価を得られるとは、とても思えない。
独身の作家だから(瀬戸内寂聴氏)、とか、夫と子どもを抱える女優だから(広末涼子氏)という属性の違いだけではない。
もはや時代は、瀬戸内寂聴氏を認めなくなってきている。「不倫」が否定されつづけてきた40年の結果である。
■なぜ不倫は、たたかれ続けるのか
では、不倫は、なぜここまで人々の心を逆なでするのだろうか?
それは、日本が、性に潔癖な社会になったからである。
こう書くと、他の国、たとえばキリスト教徒の多い国のほうが、よほど日本よりも不倫に厳しい、との反論が出るだろう。
五十嵐彰氏と迫田さやか氏の共著『不倫実証分析が示す全貌』(中公新書、2023年)が指摘するように、日本では、不倫を「間違っている」と答える割合が90%という高水準にありながらも、「他国と比較すると、日本は不倫に対して緩めの態度である」(同書、48ページ)。
どこが潔癖なのか。
それは、セックスレスの増加、および、若者の性交経験率の減少、という2つの流れにあらわれている。
■いまの日本はセックスを避ける社会
一般社団法人日本家族計画協会家族計画研究センターが2020年に実施したインターネット調査によれば、「この1年間、まったくセックス(性交渉)がないのは男性41.1%、女性49.5%」であり、婚姻関係にあるカップルでは、51.9%がセックスレスである。
日本性教育協会が2017年におこなった「青少年の性行動全国調査」では、2005年にピーク(大学生男子63.0%、大学生女子62.2%)をむかえた性交経験率は、それぞれ47.0%と36.7%まで急降下している 。
大人も子どもも遠ざかるばかりのセックスにたいして、日本で抱かれるイメージは、汚らしく、めんどくさいものでしかない。
まもなく最終回を迎える連続ドラマ「あなたがしてくれなくても」(フジテレビ系、毎週木曜22時〜)では、永山瑛太氏の演じるカフェの店長と、田中みな実氏の扮(ふん)するファッション誌の副編集長の2人がともに、セックスにたいする後ろ向きな姿勢をあらわにする。
瀬戸内寂聴氏のような「男女の性愛を余すところなく描」く作家は、出てこないし、いまの日本では、支持を集めないだろう。
■一部の性に奔放な人たちと、それ以外の人たち
不倫バッシングの理由をめぐっては、これまでも何度も語られてきたし、今回の広末氏の件についても、女優だから、と、彼女をかばう見方もある。
「もともと、日本は婚外の関係に寛容だった」とか、「日本では明治のはじめに、わずかな時期とはいえ「妾」が法律で認められていた(戸籍法)」、とか、「いまでも一夫多妻制を持つ国がある」といったかたちで、歴史や海外に照らしても、いろんな意見をくりだせる。
先に述べたように、わたしたちは、不倫の是非をネタとして食べつづけてきたし、今回は、そこに「交換日記公開の是非」や、サレ夫(不倫された夫)の涙、という新しい要素が加わり、熱が冷めない。
話題が熱さを失わないのは、広末氏や鳥羽氏のように性に自由な人たちが、ごく限られているからである。
セックスが日々の生活から消えているなかで、一部の奔放な人びとの振る舞いは、ネタとして楽しむには最適だからである。
「それ以外」、つまり、性と関係の薄いわたしたちは、自分たちの生活を脅かさず、安心して「倫理的な」=反・不倫的な意見をいくらでも堂々と並べられる。
ああでもなく、こうでもなく……。わたしのこの文章のように「不倫バッシングの理由」を探ろうとする会話もふくめて、ネタは尽きない。
■変化する日本社会をどこまで受け入れるか
フリーライターの鶴見済氏のような、「誰もがセックスをしたいもの。そう決めつけることによって、これまでの恋愛文化はなりたってきた」が、「そろそろ見なおしてもいいのではないか?」との考えもありえよう。
若い世代にとって、今回の「W不倫」は、どうでもいい話題なのかもしれない。
セックスから遠ざかれば遠ざかるほど、汚らわしいもの、もしくは、うっとうしいもの、といったイメージは、増えるにちがいない。
少子高齢化が加速するなかで、子どもの性を管理しようとする親は増えるだろうし、中年でセックスレスが半数を超える以上、年齢が上になればなるほど、性から退く人は多くなるにちがいない。
となれば、性にアクティブな限られた人たちへの視線は、ますます厳しくなるのではないか。
不倫バッシングが続くどころか、苛烈になる社会を、わたしたちは、どこまで受け入れていくのか。その是非までは、にわかには判断ができない。
———-
神戸学院大学現代社会学部 准教授
1980年東京都生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(社会情報学)。京都大学総合人間学部卒業後、関西テレビ放送、ドワンゴ、国際交流基金、東京大学等を経て現職。専門は、歴史社会学。著書に『「元号」と戦後日本』(青土社)、『「平成」論』(青弓社)、『「三代目」スタディーズ 世代と系図から読む近代日本』(青弓社)など。共著(分担執筆)として、『運動としての大衆文化:協働・ファン・文化工作』(大塚英志編、水声社)、『「明治日本と革命中国」の思想史 近代東アジアにおける「知」とナショナリズムの相互還流』(楊際開、伊東貴之編著、ミネルヴァ書房)などがある。
———-