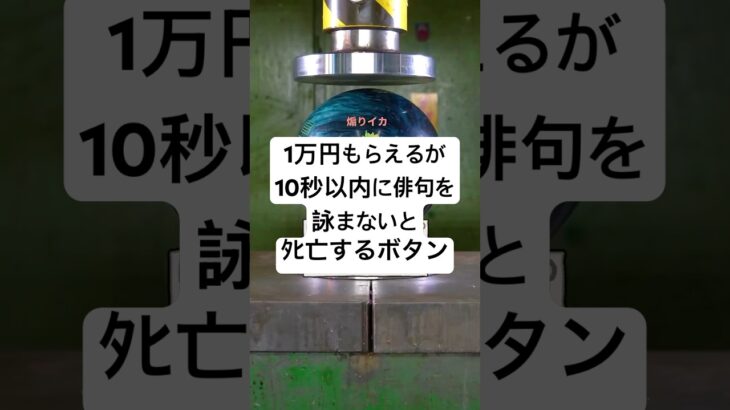あわせて読みたい
焼肉のスペシャリストが明かす「間違えた焼き方」の典型例 !
👉全体がほどよく色が変わった頃、時間をかけて焼き上げたロースは温かく、やわらかく、ふくよかな味わいの食べ物へと変貌を遂げるのである。
「A5」=「おいしい肉」とは限らない! 日本人が意外と知らない正しい“肉の選び方”とは から続く
「焼肉」は“肉質”もさることながら“焼き方”でも味が大きく変わる料理。それだけに、よりおいしい肉を味わうべく、焼き方にこだわりを持つ人も多い。しかし、そのこだわりが間違っているとしたら……。
ここでは、調理の仕組みや科学、食文化史などを踏まえた執筆・編集を行う松浦達也氏の著書『教養としての「焼肉」大全』(扶桑社)の一部を抜粋し、間違えた焼き方の典型例、そして肉種・条件別のおいしい焼き方を紹介する。(全2回の1回目/前編を読む)
◆◆◆
ていねいに焼いておいしく、乱暴に焼いてもおいしい焼き方
僕はこれまで、さまざまな雑誌やテレビ、その他メディアで焼き方の検証を繰り返してきた。業務だけで数千枚、考えながら焼き方を試してきた。もともと実験や検証が好きなおかげで、よく雑誌やウェブ記事で焼肉の検証企画のお声がかかる。以前、とある雑誌で「焼肉は何ミリカットがベストなのか」という企画を行うことになり、“精肉の名人”サカエヤの新保吉伸さんに手切りでタン、ハラミ、レバーの3種類の肉を、2mm、5mm、8mm、12mmの4パターンにカットしていただいた。ちなみにカルビやロースを除外しているのは、別の雑誌の企画でカルビとロースは検証済みだったのと、カルビやロースといった正肉は個体によって焼き方がかなり変わるからだ。
肉は一般的な焼肉店だとだいたい5~8mmくらいの厚さで切ることが多い。5mmだといわゆる並(やや薄め)、8mmだと厚切り。5mmは基本さえわかれば誰でもおいしく焼くことができるし、8mmだってていねいに焼けば、まずおいしく食べることができる。
焼肉のおいしさは結局のところ、「表面に適度な焼き目がつき、内部が適切に温まっている」状態をいかにつくるかに尽きる。
「たったひとつの確実な正解などない」
理系っぽい言い方をすると、「表面は加熱による強いメイラード反応とカラメル化のダブルの反応が起き、内部は筋線維からの水分の離水が少ない60℃程度までの加熱で多汁性を保った状態」とでも言えるだろうか。それを実現しやすいのが、5~8mm程度の厚さというわけだ。
もっとも表面に焼き目をつけるかどうかは肉質や食べる人の嗜好や体調にもよるし、ロースなどは火を入れすぎないほうがおいしく食べられる場合もある。
逆にタンやハラミなどは筋線維がタンパク質変性するまできっちり全体を加熱したほうが、持ち前のザクザクした食感を満喫できる。
すべての料理に通底することではあるが、焼肉にも「たったひとつの確実な正解などない」と考えたほうがいい。
ひとつ正解があるとすれば「安全」に焼くこと。レバーなどは内部まである程度火を入れる必要があるが、おいしくて安全を担保できる温度帯はきわめて狭い。少しでも火を入れすぎると食感になめらかさが失われてしまい、おいしく焼くのが難しい部位ではあるが、それでも安全に焼くことを心がけたい。
「乱暴な焼き方」と「乱暴に見える焼き方」の大きな差
調理の最終工程からサービス、喫食までを客自身が担当する焼肉はさまざまにある飲食業態のなかでも、客同士のコミュニケーションが求められ、それが前提となっている業態だ。
しかもおいしいものに対する執着は人によって差がある。食に執着のない人が、「俺は偉いのだ」「焼肉を知っている」と権勢を誇りたい(というか、見栄を張りたい)がためにトングを持ってしまうと、場の全員が不幸になってしまう。
たまに、ロースターの状態が調っていないのに肉を載せたり、慣れていないのに皿の肉をドバーッと焼き網の上に流し込んでしまったりする人がいる。体育会系の出身なのか、よほど腹をすかせているのかはともかく、そういう人はだいたい焼肉に対する愛情か、周囲に対する気遣いのどちらか(あるいは両方)が欠けている。
調理の最終工程を客自身が引き受ける稀有な業態といえば、ほかにも鍋料理や一部のお好み焼き店などでこうした業態があるが、欧米圏では客が調理の最終工程を引き受ける料理などほとんどない(あるとすれば、チーズフォンデュや、バーベキューの最後のマシュマロ焼きくらいだろうか。あれを調理というかどうかは別として)。
ところがまれに、乱暴な焼き方でもうまく焼けるケースがある。要は一定の条件を満たしてさえいれば、焼き方が多少乱暴だろうがおいしい焼き上がりになるのだ。とはいえ、偶然頼みではもったいない。「乱暴な焼き方」と「乱暴に見える焼き方」の間には大きな差がある。
間違えた焼き方の典型例
正真正銘の乱暴な焼き方の典型例は次のようなものだろうか。とりわけミックスホルモンのように、複数部位の盛り合わせで見かけることが多い。
【パターンA】
店員がセットしてくれた火加減ではなく、火を全開にして網の上に皿から肉を流し込む。そのままビールを飲みながらしばらく談笑。ホルモンの脂が溶けて火柱が上がるとあわてて網の上の肉をざっくり返し始めるが、火柱は収まらない。結果、炭化して焦げた部分と生に近い部分が網の上で同居している。
【パターンB】
網が十分に温まらないうちに肉を流し込む。しばらくして、肉を返そうとすると網に肉がくっついてうまくはがれない。強引にはがしたところ、肉片が網にくっついてしまって、せっかくの焼き目まで取れてしまう。全体になんとなく火は入っているが、焼肉らしい香ばしさがない。
Aは主に流し込んだ後の対応が悪く、Bは主に流し込む前の状態の見極めができていない。ざっくり言うと、網の上の温度が安定しないところに肉を置いてしまうと、焼き加減のコントロールが難しくなる。「ていねいに焼く」ということは「自分で面倒を見ることのできる量の肉を網に載せる」ということだ。
大阪では流し込んで焼く人が多い
焼肉を焼くときは網の適正な温度というものがあり、その温度帯を外すと肉を焦がしてしまったり、逆に表面に焼き目をつけたいのにできなかったり、望ましくない焼きムラがついてしまったりする。
ただし、面白いことに焼き上手な人は、ドバーッとやってもおいしく焼き上げられるのだ。どう焼いているのだろうか。
あちこちの店で比較的“ドバーッ”が行われているのが大阪だ。とりわけ両サイドにガスの筋が2本走っていながら、スリット入りの鉄板ではなく、焼き網で焼くタイプの店(三重県松阪市の鶏焼肉専門店にこのタイプのガスロースターが多い)で時折見かける。こうした焼き台は東京にはあまりないため、初めて見たときは戸惑ったが、このタイプの焼き台で流し込んでいる人が多い。
まとめ焼きで上手く焼くコツ
両サイドにガス火が走っているロースターでは一般的にはスリット入りの鉄板が使われていることが多い。
径の細い焼き網×ガスロースターだとセンター部分の温度がそれほど上がらないため、網を通じて肉にまで温度が伝わらないのだ。がっつり肉を焼くことのできるエリアは二の字になったガス火の直上しかなく、これ以外の部分はほとんど保温ゾーンになってしまう。
関西の焼肉店でドバーッと流し込む人は、こうした焼き網ロースターに慣れている人が多い。ガス火の直上のみ強火で中央部が弱火だから強火の部分で焼き目やちょっとした焦げ目をつけ、中央部で休ませる間に肉全体に熱を回すという焼き方だ。
ほんのわずかの焦げ目の味がアクセントに
ちょっと手はかかるが、焼く場所が明確で休ませる場所が広いということは、焼き方次第で一度に大量の肉を焼くことができる。シビアな焼きには不向きかもしれないが、大勢でロースターを囲み、バンバン焼いてどんどん食べ、ガンガン飲むようなときには、むしろ向いているかもしれない。
まとめて焼いて8割方仕上げて、中央の休ませゾーンに退避させる。最後は食べたい人が火の直上で仕上げの焼き目をつけ、酒を飲み、メシを食う。火の上だけが焼き台でセンターが大皿のイメージ。空いた焼き台には次々と新たな肉を放り込む。これは乱暴に見えてかなりテクニカルな焼き方と言える。香ばしい焼き目に加えて、ほんのわずかの焦げ目の味がアクセントとなって酒とメシが進みまくる。さすがは関西、(牛)肉の本場である。
時間をかけて焼き上げる「飲むロース」
もうひとつ、東京・銀座にある某老舗焼肉店のロースもまとめ焼きだ。この店はスタンダードなスリット入り鉄板×ガス火。皿に山盛りにされたこの店のロースは目分量ながら4人盛りで200g以上はあるだろうか。
この「飲むロース」とも称されるロースを、皿からザバーッと鉄板上に流し込む。この時点でこの店の焼き方を知らない人は、雑に見えてしまうだろう。しかしそうではない。この焼き方はこの店のロースならではの焼き方なのだ。
まずこちらのロースは、雑に流し入れてはならない。ガス火の直上を避けて、中火ゾーンのセンターに一文字になるように肉をまとめる。それを下から上へ、下から上へと何度も上下を返しながら、火の直上には当たらないよう、全体をじわじわと加熱していくのだ。
かくして全体がほどよく色が変わった頃、時間をかけて焼き上げたロースは温かく、やわらかく、ふくよかな味わいの食べ物へと変貌を遂げるのである。
(松浦 達也)