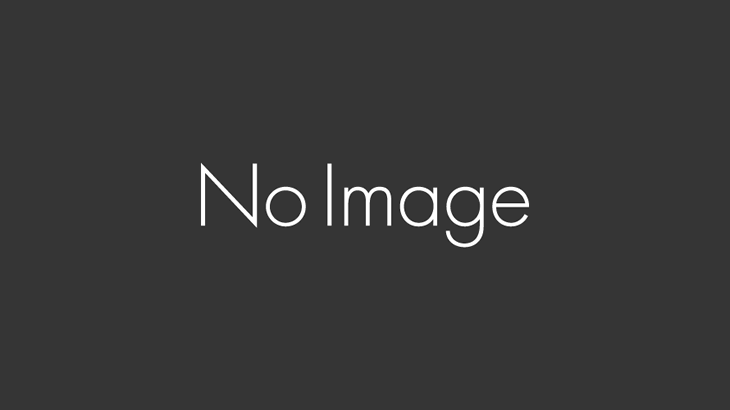あわせて読みたい
中国の本音「長期化は避けてね」長引く内需不足と世界が進める「脱チャイナ政策」で国内ボロボロ…報復で自国も大ダメージ
(略)
アジア新興国の重要性が高まっている
日本は観光市場の多角化を推進しているが、日本の輸出相手として中国は米国に次ぐ2位で全体の約2割を占める。輸入では最も多い相手であり、レアアースの多くを頼る中国の存在は別格と言える。日本は「脱中国依存」の取り組みが急務となるが、短期的にはコスト増大が避けられない。 2010年に尖閣諸島周辺で中国漁船が海上保安庁の巡視船と衝突した際には中国がレアアースの輸出制限を行った。中国はレアアースの国別精錬比率で9割以上を占める。
ただ、誤解を恐れずに言えば「チャイナリスク」は、かねて指摘されてきたものだ。これまで中国は企業の進出先としても熱い視線が向けられてきたが、今は企業もカントリーリスクを重く見ている。
帝国データバンクが11月20日公表した意識調査によれば、現在の重点地域としては「生産」「販売」で中国がトップであるものの、今後はベトナムやインド、インドネシアなどのアジア新興国の重要性が高まっていることがわかる。
それによれば、生産や販売の拠点など直接的に進出している企業は9.5%で、業務提携や輸出など間接的に海外進出している企業は13.8%だった。興味深いのは、現在海外進出している国・地域で生産拠点として「最も重視する進出先」を聞いたことへの回答だ。
「中国」は16.2%と最も高かったが、コロナ禍前の2019年時点(23.8%)と比べて大きく低下した。
日本への報復措置は中国側にもダメージ
代わりに、「ベトナム」(7.9%)、「タイ」(5.3%)、「台湾」(2.7%)と他のアジア諸国・地域が上位に食い込んでいる。
販売拠点として「最も重視する国・地域」も中国(12.3%)でトップなのは変わっていないが、2019年調査(25.9%)と比べると落ち込みが目立つ。今後重視する進出先として検討する可能性がある国・地域としては、生産拠点に「ベトナム」をあげる企業が最も多かったという。中国のカントリーリスクを考えれば当然の結果だろう。帝国データバンクは「成長市場への期待が高まっており、『チャイナ・プラスワン』などの動きを反映したものと言えよう」としている。
今や世界2位の経済大国となった中国だが、国家統計局が10月20日に発表した2025年7〜9月の国内総生産は、実質で前年同期比4.8%に減速している。長引く内需不足の影響は深刻だ。日本への報復措置は中国側にもダメージとなり、長期化は避けたいのが本音だろう。もちろん、関係修復が遅れれば遅れるほど、日本経済への打撃は大きくなる。
日中関係はしばらく「冬の時代」
ただ、今回の中国サイドの報復は高市首相が11月7日の衆院予算委員会での発言が原因だ。首相は台湾有事の際の想定を問われ、「戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば『存立危機事態』になりうるケースであると、私は考える」と答弁し、中国側の反発を招くことになった。中国外務省報道官は「日本側が発言の撤回を拒否し、さらに間違いを犯せば、中国側は厳しい断固とした対応措置を取らざるを得ない」と牽制している。
科学的根拠に基づく説明が可能な事案であれば、日本側が正確な説明をすれば問題は終わる。だが、今回は「首相の発言」そのものを問題視し、それを撤回しろと迫っているものだ。それだけに、日本政府内には「これは難しいことになる」と長期化する可能性があると見る人も少なくない。
高市首相は、内閣総理大臣としての靖国神社参拝を現在のところ見送っているものの、やがて現実化するとの見方も広がる。日中関係はしばらく「冬の時代」を迎えそうだ。
(略)
日中関係の「冬の時代」は、容易には終わりそうにはない。中国側が求める「発言の撤回」は、日本の主権に関わる問題であり、高市政権がこれに応じる可能性は極めて低いだろう。一方で、内需不足に苦しむ中国経済にとって、日本への報復措置の長期化は自国経済への更なる打撃となり得る。
全文はソースで
佐藤健太
https://news.yahoo.co.jp/articles/23ada95a1d3598bb5bd5eca61c52bbbe94ddc645?page=1