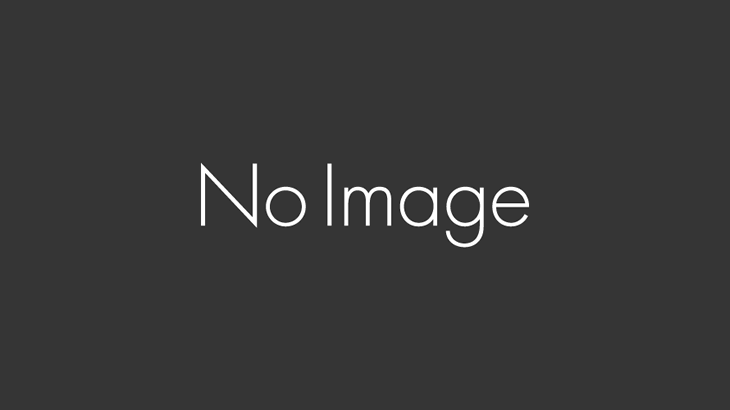あわせて読みたい
 |
広がる共働き、専業主婦はなぜ減った?◆選択迫られる女性、若者が考える夫婦のかたち#令和に働く 戦後80年で夫婦の働き方は大きく変わりました。農家や家族単位の自営業が多かった終戦直後から、専業主婦世帯が増えた高度経済成長期を経て、共働き世帯が… (出典:時事通信) |
|
専業主婦(せんぎょうしゅふ、英: stay-at-home mother or SAHM)は、家事(炊事、洗濯、掃除など家庭における日常生活運営)を専業としたライフコースの女性。主婦の中でも妊娠・出産を機に稼業から離れて、家事・子育てを引き受け、夫の稼業を支えている既婚女性・内縁女性。男性の場合は…
20キロバイト (3,065 語) – 2025年9月19日 (金) 09:19
|
1 煮卵 ★ :2025/10/13(月) 17:37:36.69 ID:RWhepuJv9
◇高度経済成長期に誕生した専業主婦、ピークで6割
総務省の統計によると、専業主婦世帯(雇用者の夫と無職の妻)は1980年の1114万世帯から2024年には508万世帯に減少。一方で、共働き世帯(夫婦ともに雇用者)は1990年代に専業主婦世帯を逆転し、2024年には1300万世帯と専業主婦世帯の2.5倍に増加した。
なぜ専業主婦世帯は減り、共働きが広がったのか。家族社会学に詳しい中央大文学部の山田昌弘教授は経済情勢の変化が背景にあると語る。
国勢調査によると、1950年の日本では働く人の45%が農業に従事。山田教授によると、都会でも町工場や商店を家族で営む世帯が多く、この頃の女性は農作業や家業に働き手として関わり、家事や育児は作業の合間に家族全体で担っていた。
変化が訪れたのは50年代後半~70年代前半の高度経済成長期。工業化が進み企業から雇用される「サラリーマン」が誕生し、男性が家の外で長時間働くことで、家計を支えるようになった。家庭では家事と育児を担う「専業主婦」が登場し、「ピークだった75年には既婚女性の約6割を占めました」と山田教授。この時代に「男性は外で働き、女性は家庭を守る」といった性別による役割意識が生まれたと指摘する。
◇共働きのきっかけはオイルショック
しかし73年に起きた第1次オイルショックで、日本の経済成長にブレーキがかかる。山田教授は「男性のみの収入では家を購入したり、子どもの学費を賄ったりできなくなった。女性も働かざるを得なくなり、75年以降、共働きが増え始めます」
女性が働く場は広がっていき、経済的なゆとりのためだけではなく、社会で活躍することでやりがいを感じる女性も増え始めた。職場での男女平等を求める声が高まり、85年には男女雇用機会均等法が成立。女性にも総合職や技術職への道が開かれ、97年の改正では採用や昇進における男女差別が禁じられた。
一方、働く女性が増えたことで仕事と家庭の両立問題も浮かび上がった。そこで、92年施行の育児休業法では子どもが1歳になるまで休業できると定め、育児との両立を後押しするようになった。労働力不足や経済の停滞を打ち砕こうと、安倍晋三政権は2013年に成長戦略の柱に女性活躍を位置付け、保育所の整備や育休後の職場復帰支援を進めることで女性が働き続けられる環境を整えていった。
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/92a47936c86fff4a89dd81b8b45ed857b1558a10
[時事通信]
2025/10/12(日) 11:02
※前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1760318622/