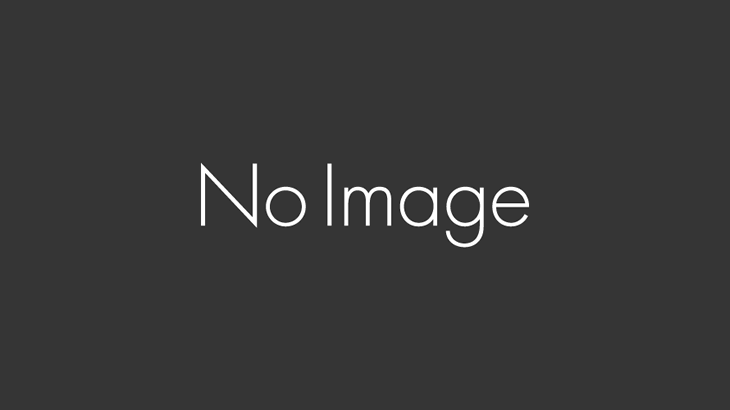あわせて読みたい
【ノーベル症】「K~」と称するワードが流行っているが「K科学」はない=韓国メディアの社説
国籍別では4人の米国人と2人の日本人、英国人・フランス人・オーストラリア人がそれぞれ1人ずつ受賞し、所属の大学・研究所は米国が6か所、日本が2か所、オーストラリアが1か所である。
韓国は最近、各分野で収めた成果や世界的な注目度が高まる中「K~」と称するワードが流行っているが、こと科学に関してはそれが通用しないことがあらためて証明された。
毎年ノーベル賞が発表されるごとに「今回も…」と受賞失敗の原因を分析し対策づくりを訴えるのが恒例行事として定着しているが、ことしもそのようになった。
最近はそのような訴えさえ鎮(しず)まった雰囲気だが、「ノーベル科学賞の実績は、基礎研究レベルの重要な指標の一つだ」という点を踏まえると、いまやわが政府と学会はこれまでとは異なった危機意識を持つべきだ。
一方、日本はわれわれとは対照的にことし2人の受賞者を輩出した。日本はこれまで、物理学賞12人・化学賞9人・生理医学賞6人の計27人が科学賞を受賞している。
日本のメディアによると、今回の受賞者2人はその研究が独創的なため、初期には批判を受けていたという。読売新聞は「科学の世界は短期間で成果が出ないことが多い。研究当時はどの部分が役立つかわからない中、後になって応用できることが発見される事例が少なくない」という論評を掲載した。
「政府の長期的な計画や投資、創意的で粘り強い研究を奨励する学会の風土、産学官の有機的な協力が、日本の科学発展の土台となっている」というのが、日本メディアの分析である。
イ・ジェミョン(李在明)政権は、来年度の国家研究開発(R&D)予算を前年比19.3%ポイント増の過去最高額で編成した。前政権で削減され物議を呼んだことを思えば喜ばしいことだが、まだもって様々な面で不十分だ。
生理学・医学賞を受賞した大阪大学の阪口志門教授は、日本政府に対し「基礎科学への支援が足りない」とし「ドイツに比べ3分の1という水準だ」と指摘した。
また「若手の研究者や有力な論文が減っている」と、日本メディアからも指摘されている。日本さえもこのような状況である。
基礎研究への長期的投資と世界最高水準を達成する国家的ビジョンは、いまや「選択ではなく必須」である。
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 96