あわせて読みたい
阪大悲願のノーベル賞受賞者 「世界トップの坂口先生を呼ばないと」
2024年度までの日本のノーベル賞受賞者は、個人では28人(米国籍の3人を含む)いるが、阪大の学部卒業生や在籍中の研究者で受賞した人はいなかった。
過去に一度、期待が大きく膨らんだ瞬間があったのは11年。同年のノーベル生理学・医学賞は細菌やウイルスの侵入に対抗する「自然免疫」などを研究した米仏の3氏に贈られた。当時、この分野の研究者が選ばれるとの見方が強まっており、中でも審良(あきら)静男・阪大特任教授(72)が世界的な業績を残していたが、惜しくも対象から外れた。
そうした経緯もあり、阪大関係者にとってノーベル賞受賞は念願だった。
今回受賞が決まった、坂口志文氏を阪大免疫学フロンティア研究センターに招へいしたのが審良特任教授だった。「制御性T細胞は現在、免疫学の中心になっている。阪大を日本一の免疫学の拠点にするためには、世界のトップを走っていた坂口先生を呼ばないとダメだと思った」と振り返る。「研究に対して信念があり、最初の制御性T細胞の発見から何十年も研究を続けているのは坂口さんだけだ」と受賞を喜んだ。
一方、阪大は1949年にノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹氏を「関係者」としている。湯川氏は京都帝国大(現在の京都大)を卒業後、33~39年に阪大の前身である大阪帝国大で講師、助教授を務めた。
受賞時は京都帝大の教授だったが、大阪帝大の講師だった34年に発表した中間子論に関する論文がノーベル賞受賞につながり、38年には理学博士の学位も取得しているため、関係者と位置づけている。
毎日
https://news.yahoo.co.jp/articles/832cadc92eeff8fd7461f6e6257ecd58b1c04081
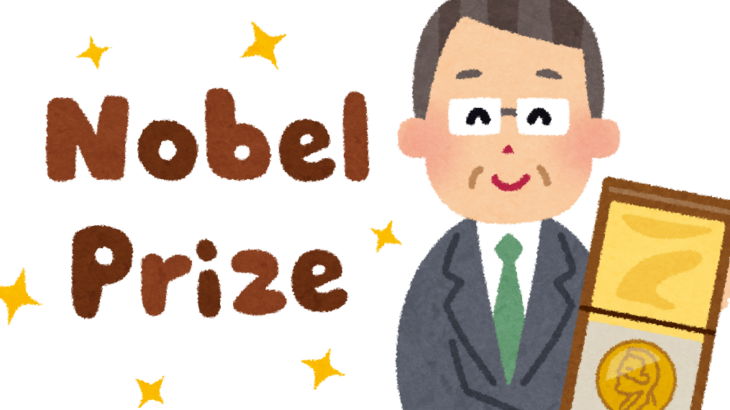






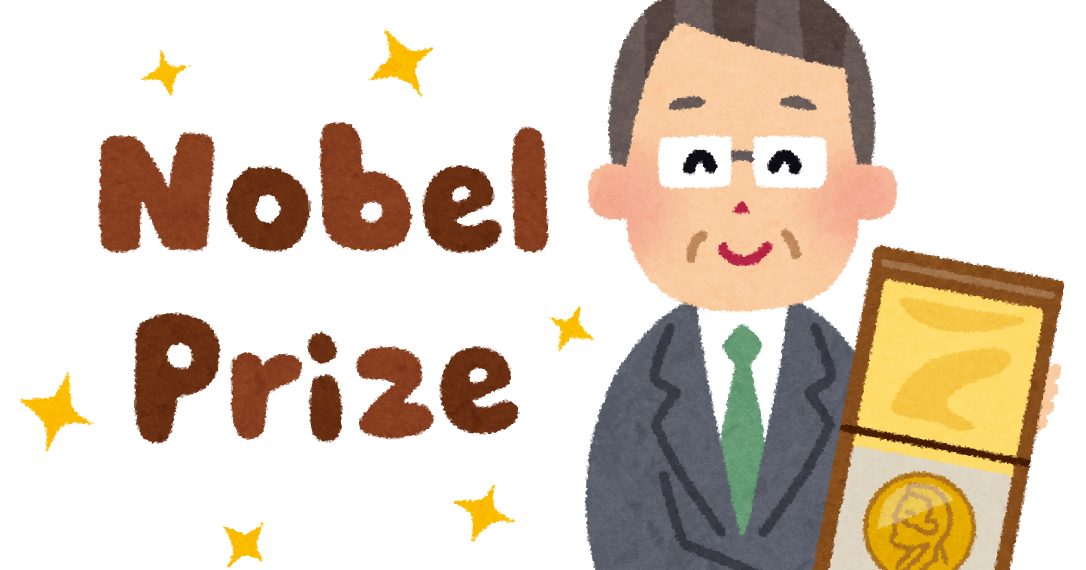
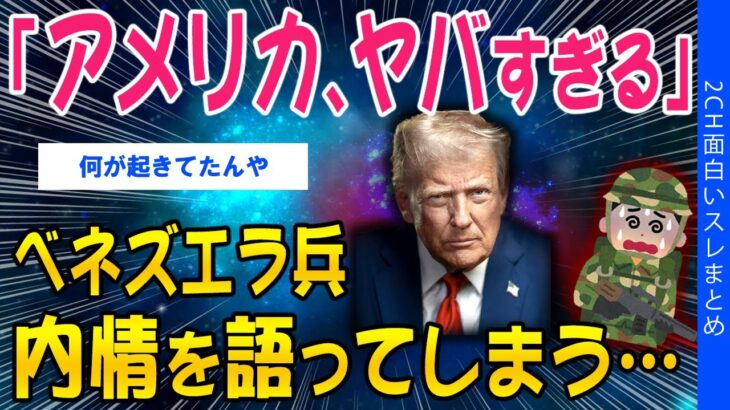
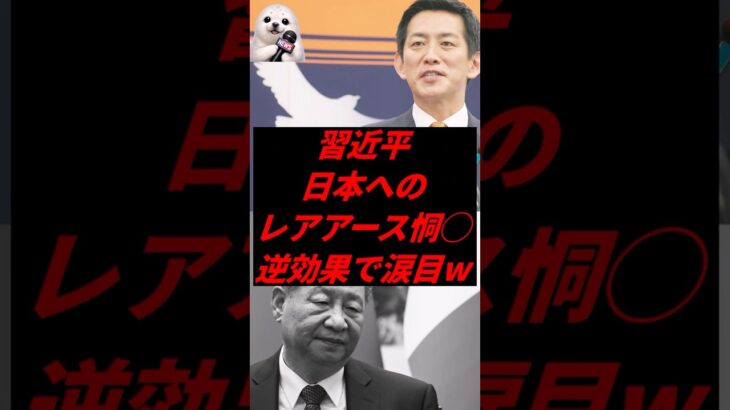

![【衝撃】ホリエモン、AIの進化で真っ先になくなる職業とは? 「俺が経営者だったら最初に切る」 [冬月記者★]](https://trivia.awe.jp/wp-content/uploads/2026/01/ai-1-730x410.jpg)

