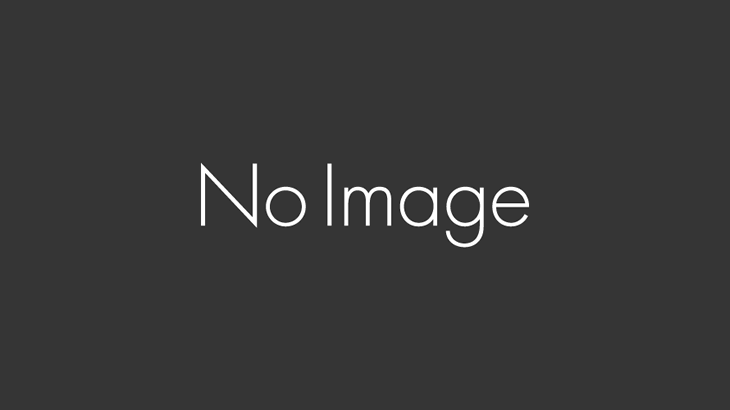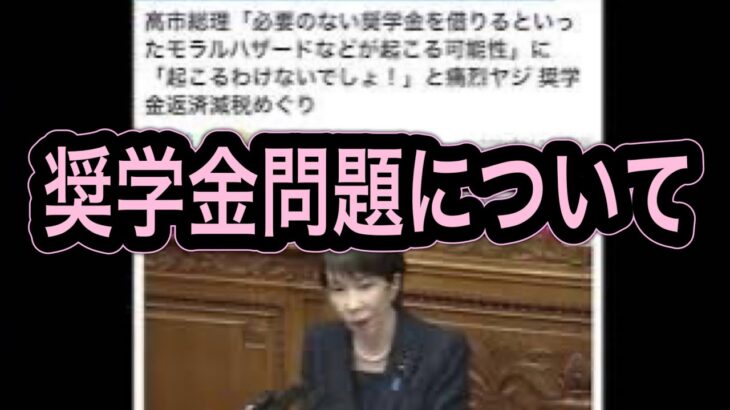あわせて読みたい
東南アジアで米国の影響力が低下、中国が米国抜き支配的な影響力
オーストラリアのローウィー研究所が、年次報告書「アジアパワー指数(Asia Power Index:API)」の一環として、9月25日、初めて「東南アジア影響力指数(Southeast Asia Influence Index:SEAII)」を発表した。
これによると、中国は貿易・投資・外交などを一貫して展開し、米国を抜き東南アジア諸国にとって最も影響力のあるパートナーとなった。
対照的に米国は、トランプ政権の一貫性のない「継ぎはぎ」外交・安全保障政策によって、この地域における影響力をさらに低下させる可能性が高いと指摘している。
(略)
SEAIIは①経済関係、②防衛ネットワーク、③文化的影響力、④外交関係、⑤地域的関与の5要件に基づき、東南アジア11か国に対する影響力のある関係上位10か国の相対的な重要性を計測したものである。
同時に、東南アジア各国間の近隣関係とその影響力のダイナミクスにも焦点を当てている。
東南アジアで最も影響力のある10か国
■東南アジア影響力指数(SEAII)
ローウィー研究所が発表したSEAIIは、下記の通りである。
順位 国 影響力指数
1 中国 65.3
2 米国 64.4
3 日本 47.9
4 オーストラリア 38.8
5 マレーシア 36.6
6 シンガポール 35.7
7 インドネシア 34.8
8 韓国 33.8
9 タイ 32.0
10 ベトナム 29.7
■主要国の影響力(分析)
中国は東南アジアのあらゆる場所に存在する
中国は、 少なくとも2017年以降、ほぼすべての国にとって最大の貿易相手国、この地域への民間投資の重要な供給源であり、最大の強みは経済関係にある。
中国は、地域貿易を大きく支配しており、東南アジアへの輸出の26%、輸入の20%を占めている。
また、東南アジア全域にわたる一貫した外交によって存在感を拡大し、同地域全体で最も影響力のある大国であり、ほとんどの国にとって主要なパートナーである。
そのため、中国は東南アジアの指導者や外相にとって最大の国際的訪問先となっている。
しかし、特に南シナ海において領土問題を引き起こしていることから、ほとんどの国との広範な防衛ネットワークは未だ構築されておらず、中国が地域を完全に自国の影響下に置いているとは見られていない。
(略)
米国は、この地域において2番目に影響力のあるパートナーであるが、その影響力は地域によって大きく異なる。
タイとはマニラ条約によって伝統的な同盟関係にあり、フィリピンとシンガポールは米国の安全保障・防衛上の不可欠なパートナーである。
他方、この地域の多くの地域、特に中国の影響力の大きいカンボジアやラオスといった大陸部の東南アジアの小国において、米国は次第に周縁的な存在と見なされつつある。
また、米国のこの地域における貿易の比率は十数パーセントにとどまり、カンボジアとラオス、ミャンマーでは、中国の影響力は米国を60~150%上回るとSEAIIリポートは説明している。
さらに、「トランプ政権による関税、対外援助削減、国際教育などといった外交政策は、米国とこれらの国々の間の断絶をますます深める結果となる可能性が高い」と警告している。
トランプ政権の現政策の継続は、東南アジアにおける米国の影響力をさらに弱めることになろう。
(略)
日本はインド太平洋諸国をリードする
米国と中国に加え、日本、オーストラリア、インド、韓国の「ミドルパワー4か国」が東南アジアで応分の影響力を発揮している。
しかし、地域全体に多面的な存在感を持つのは日本だけであると指摘している。
近年、日本は中国に相対的な経済的影響力を奪われているものの、この地域における安全保障上のパートナーとしての重要性をますます高めている。
全文はソースで