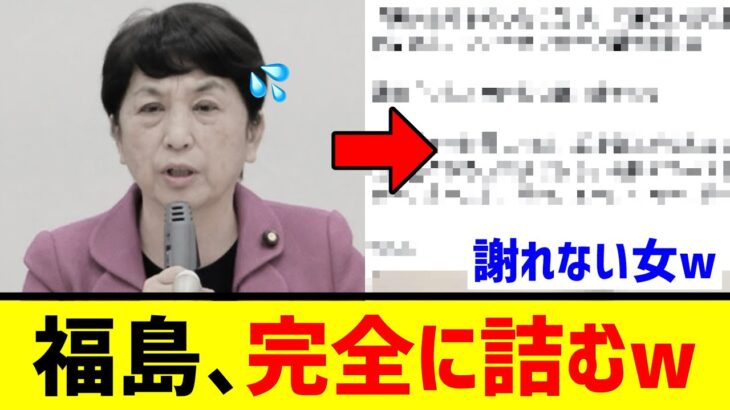あわせて読みたい
「鉄道オタク=社会不適合者」は時代遅れ? “少子化ショック”の大学を救う尖った知性の経済価値とは
https://merkmal-biz.jp/post/98330
■自己アピール型鉄道オタクの台頭
鉄道は、移動手段ではない。そこには、技術、歴史、文化、そして人々の記憶が凝縮されている。しかし、近年、一部の鉄道オタクによる過激な行為や偏った言動が、この豊かな世界を歪めてはいないだろうか。本連載「純粋鉄オタ性批判」では、本来の鉄道趣味の姿を問い直し、知的好奇心と探究心に根ざした健全な楽しみ方を提唱する。万国の穏健派オタクよ、団結せよ!
鉄道趣味の多様化が進んでいる。撮影に特化した「撮り鉄」、音に魅了される「音鉄」、模型収集を楽しむ「模型鉄」など、ジャンルは年々細分化されている。
鉄道関連イベントでも、若年層の姿が目立つようになった。現場の鉄道職員によれば、撮り鉄の6~7割は
「中高生」
という実感があるという。背景にはデジタル環境の変化がある。性能の高いカメラが手頃な価格で手に入るようになり、写真や動画をネット上に公開するためのスキルも、今や中高生レベルで習得可能になった。大学生になると、アルバイト収入を鉄道趣味に投じることで、さらに活動の幅が広がる。
鉄道模型の世界でも状況は同じだ。ジャンク品を中古市場やネットで安く入手し、走行させるだけなら十分に楽しめる時代となった。
インターネットに慣れ親しんだ若年層は、撮影した写真やコレクションをSNSや個人サイトで発信する手段を持つ。これにより、
「自己アピール型オタク」
と呼ばれる新たな鉄道ファン層が台頭してきた。この潮流の背景には、教育政策の変化もある。
・情報リテラシー教育
・表現力重視のカリキュラム
が、発信するオタクを育ててきた側面がある。若年層による鉄道趣味の進化は、娯楽の範囲を超え、社会や市場への影響力を持ち始めているのだ。
鉄道オタク増加の入試戦略
文部科学省の試算によると、2040年度の大学進学者数は2017年度から12万4000人減り、50万6000人になる見込みだ。大学の定員が現状のままなら、東北を中心に入学定員充足率が60%台となる地域が増え、地方都市の大学は厳しい経営環境が続く。
最近では女子大学や短期大学の閉校が相次ぎ、メディアでも報じられている。大学側は生き残りをかけて必死の対応を迫られている。多くの学生を確保し、定員割れを避けたいのが本音である。
そのため、学力が一定程度必要な大学入学共通テストや冬季の一般入試を避け、推薦系の入試に注力する傾向が強まっている。1990年代以降、
・一芸一能入試
・AO入試(現・総合型選抜)
が台頭した。AO入試は「Admissions Office Examination」の略で、米国の大学で導入された。成績だけでなく、人物像や興味、才能、将来の活躍可能性を多面的に評価する方式だ。エッセイや推薦状、ポートフォリオも重要な評価材料となる。
日本では当初、慶應義塾大学などが採用し一定の機能を果たしていた。しかし少子化の影響もあり、多くの大学が経営改善の手段としてAO入試を乱用した。結果、
「学力重視の入試を避けるバイパス」
となってしまった。この流れは高校にも波及し、AOに近い推薦型入試が増加している。大学教員の話では、推薦系入試で
「鉄道趣味をアピールする若者」
が増えているという。
・撮り鉄としてのコンクール入賞
・全国高等学校鉄道模型コンテストでの受賞
・鉄道趣味でのメディア出演
などが武器になる。高校の課題研究や総合学習の成果として、受賞やメディア経験を持つ学生も多い。
さらに、ウェブサイト運営やプレゼンテーション能力といったコミュニケーション力を強調する若者も増加中だ。鉄道オタクの自己アピールが強まっており、なかには飛行機やバスの趣味を活かす学生もいるという。
少子化対策としての個性戦略
鉄道オタクとしての個性を大学入試でアピールできるなら、若者にとって進学のモチベーションになる。文部科学省の予測では、2040年度の大学進学者数は50万6000人に減少する。一方で、18歳人口のおよそ30万人が大学には進学しない現実もある。
大学教員によると、オタク気質の若者は、
「社会性」
さえ身につければ好きなことを強みにして活躍できる可能性が高いという。卒業研究でも、好きな対象に打ち込む学生のパフォーマンスは高い傾向がある。
原稿執筆中、東京電機大学が「とんがりAO」と名づけた新たな総合型選抜入試の導入を発表した(『毎日新聞』2025年7月28日付け。大学によるプレスリリースは2025年1月)。
※以下出典先で







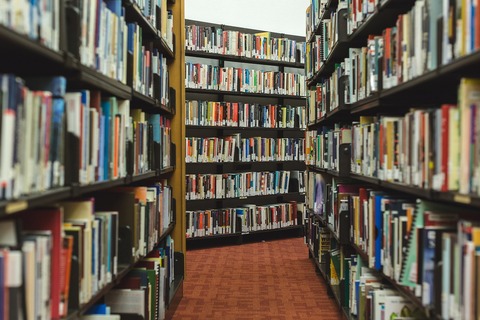
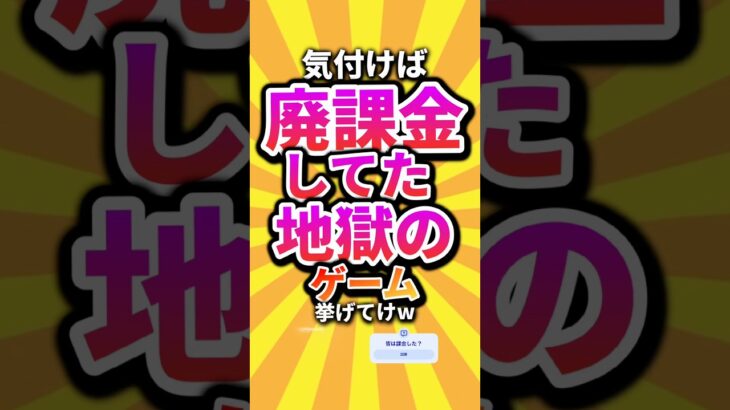
![【衝撃】[実話]東日本大震災後の被災地でタクシー運転手が遭遇した心霊現象…3.11後に起きた心霊怪奇体験5選](https://trivia.awe.jp/wp-content/uploads/2026/02/1287939-730x410.jpg)