あわせて読みたい
【教育】「死体を煮て溶かしている」『ごんぎつね』の読めない小学生たち…“いま学校で起こっている”国語力崩壊の惨状
文春オンライン
少年犯罪から虐待家庭、不登校、引きこもりまで、現代の子供たちが直面する様々な問題を取材してきた石井光太氏による、教育問題の最深部に迫った『 ルポ 誰が国語力を殺すのか 』(文春文庫)の一部を抜粋して紹介。いま、子供たちの〈言葉と思考力〉に何が起こっているのか。(全2回の1回目/ 後編 に続く)
◆ ◆ ◆
『ごんぎつね』の読めない小学生たち
都内のある公立小学校から講演会に招かれた時のことだ。校長先生が学校の空気を感じてほしいと国語の授業見学をさせてくれた。小学4年生の教室の後方から授業を見ていたところ、生徒の間に耳を疑うような発言が飛び交いだした。
「この話の場面は、死んだお母さんをお鍋に入れて消毒しているところだと思います」
「私たちの班の意見は違います。もう死んでいるお母さんを消毒しても意味ないです。それより、昔はお墓がなかったので、死んだ人は燃やす代わりにお湯で煮て骨にしていたんだと思います」
「昔もお墓はあったはずです。だって、うちのおばあちゃんのお墓はあるから。でも、昔は焼くところ(火葬場)がないから、お湯で溶かして骨にしてから、お墓に埋めなければならなかったんだと思います」
「うちの班も同じです。死体をそのままにしたらばい菌とかすごいから、煮て骨にして土に埋めたんだと思います」
生徒たちが開いていたのは国語の教科書の『ごんぎつね』だ。作家の新美南吉が18歳の時に書いた児童文学で、半世紀以上も国語の教材として用いられている。生徒たちはその一節を読んだ後、班ごとにわかれてどういう場面だったかを話し合い、意見を述べていたのである。
『ごんぎつね』の話を覚えていない方のために、おおまかな内容を記そう。
ある山に、「ごん」という狐が住んでいた。ごんは悪ふざけが好きで、近くの村の人たちに迷惑ばかりかけていた。その日も、小川で兵十という男性が獲ったうなぎや魚を逃がしてしまった。
10日ほど経った日、ごんは兵十の家で母親の葬儀が行われているのを見かける。兵十が川で魚を獲っていたのは、病気の母親に食べさせるためだったのかと気づく。自分はそれを知らずに逃がしてしまったのだ。ごんは反省し、罪滅ぼしのために毎日のように兵十の家へ行き、内緒で栗や松茸を置いてくる。
そんなある日、兵十は自分の家にごんが忍び込んでいるのを目撃する。彼は、いたずらをしに来た、と早とちりして火縄銃で撃ち殺す。だが、土間に栗が置かれているのを見て、これまで食べ物を運んでくれていたのがごんだったことに気づき、その場に立ちすくむ――。
続きは↓
「死体を煮て溶かしている」『ごんぎつね』の読めない小学生たち…石井光太が明かす“いま学校で起こっている”国語力崩壊の惨状 https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/bunshun/nation/bunshun-80431









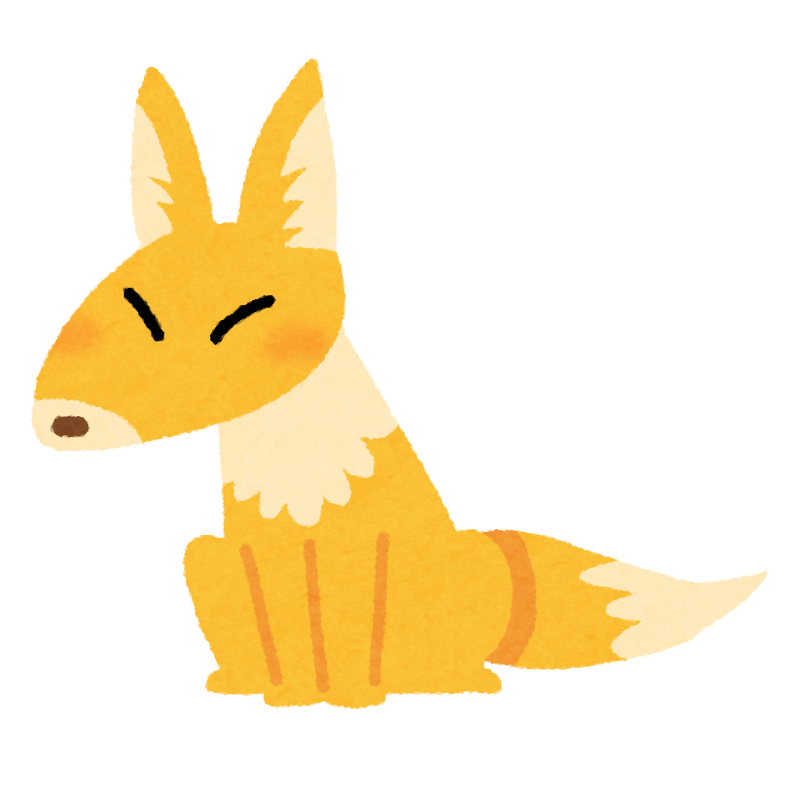

![【衝撃】ホリエモン、AIの進化で真っ先になくなる職業とは? 「俺が経営者だったら最初に切る」 [冬月記者★]](https://trivia.awe.jp/wp-content/uploads/2026/01/ai-1-730x410.jpg)



