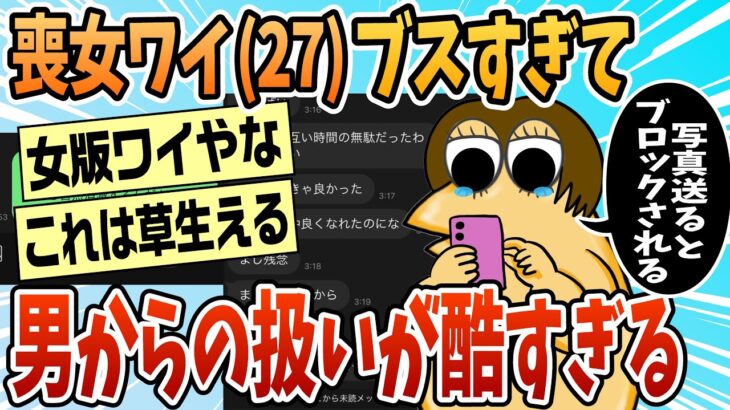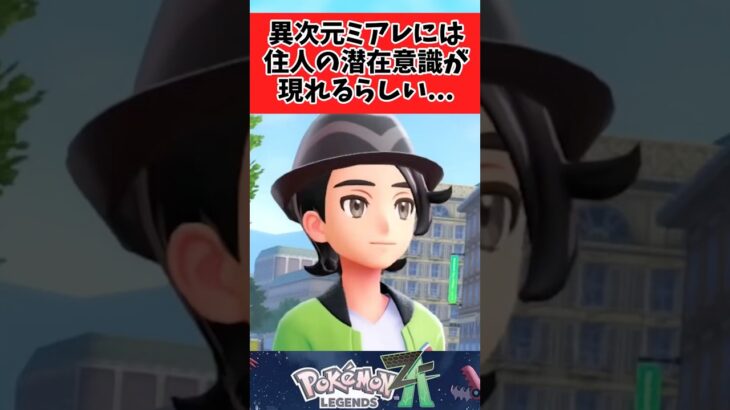あわせて読みたい
外国人留学生への「生活費支援見直し」を賞賛する日本人のヤバさ。「大学のレベルが低い国」の末路とは
6月26日、文部科学省から「日本の博士課程に進学する学生に対する経済支援制度について、生活費を留学生には支給しない方針」が示されました。
対象は日本人学生に限定される方向で見直される見通しです。
現在、受給者の40%程度を占める留学生。生活費として支援されるのは240万円とされており、毎月20万円ほど支援がなくなる計算になります。
博士課程の学生は、求められる専門的知識・技能のレベルが非常に高い一方で、職業的に不安定であり、経済的にも困窮するケースが多い。
私の知り合いにも「経済的に不安定である」と、大学院進学をあきらめ、一般企業に就職した方がいます。
研究費に関しては日本人・留学生双方に支援が継続されるとのことですが、おそらく博士課程への進学動機は薄れることでしょう。
(略)
よく「働きもせず大学院に行くのだから自己責任」といった話も耳にします。
ですが、これもお話にならない。日本は国土が広いわけでもなく、資源が豊かなわけでもない。であれば、技術やノウハウで稼がないと道はないでしょう。
そのためには、人生をかけてフロンティアを探究し、知の領域を押し広げ続ける人々の活躍が欠かせません。
「留学生支援打ち切り」がきっかけで大学の力が下がる可能性も
私の懸念は2つ。
「留学生の足が遠のき、優秀な学生が集まりにくくなるのではないか」、そして「留学生だけだった支援打ち切りが『年収○万円以上の所得を持つ学生』『○歳以上の学生』などへ拡大されるのではないか」という懸念です。
どちらも、研究機関としての大学の力を高めるどころか、下げるような施策であるように感じます。
お金が問題で研究をあきらめるような事態になってしまえば、それこそ不利益となるでしょう。
(略)
私は研究を道半ばであきらめたからこそ、過酷な研究者修行の道を進み続ける方には、せめてあたたかな祝福と、苦労に見合った栄光が用意されていてほしい。
古来より、先人の業績を基に新たな知見を得ることを「巨人の肩に乗る」と喩えられます。果たして、次世代の巨人が育つ土壌は、この国に残っているのでしょうか。
<文/布施川天馬>
https://news.yahoo.co.jp/articles/d28080b8602455ab82360c61a74d03eb779d2393?page=1