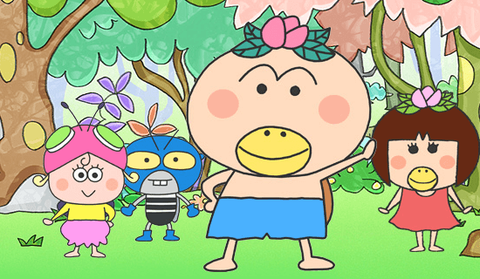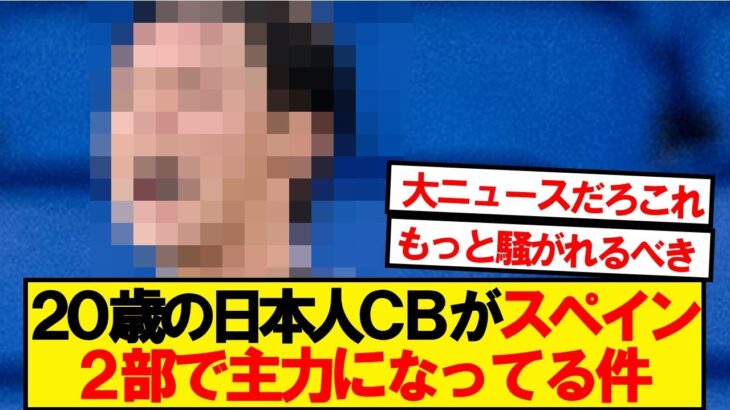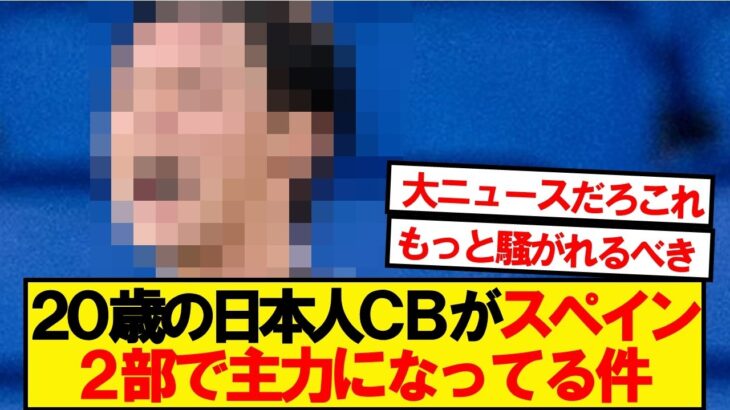あわせて読みたい
数学教授が大学で基礎的な「四則(混合)計算」を講義する理由
芳沢 光雄 数学・数学教育
4月16日の朝日新聞朝刊に掲載された記事『一部私大の授業「義務教育のようだ」財務省「助成見直しを」』において、やり玉に挙がった内容には「四則(混合)計算」の指導が含まれるようで、多くの識者による強い意見が表面化している。
それらの意見では、「四則(混合)計算は極めて易しい内容であるにも関わらず、あえて大学の授業で扱っている」という共通の意識がある。
もっとも、その先の助成金に関する考え方はそれぞれ異なっているように見える。
本稿では筆者の実践などを通して、その意識に疑問を呈するものである。
筆者は一昨年の3月に大学教員人生45年に幕を閉じたが、その間に5つの大学に専任教員として勤務し、他に非常勤講師として5つの大学にも勤務し、合わせて約1万5千人を対象として数学の授業を担当してきた(文系理系半々)。
それらとは別に1990年代後半から、全国各地の小中高校で合わせて約1万5千人に、算数・数学に興味・関心を高める目的をもって「出前授業」を行ってきた。
理学部数学科に所属した22年間では、四則(混合)計算について復習する授業は無かったが、最後の本務校のリベラルアーツ学群では、専門の数学、教職の数学、ゼミナール、リベラルアーツの基礎、などのほかに「数の基礎理解」という授業を定年まで行い、そこでは四則(混合)計算についても堂々と講義した。
その授業の講義内容は、拙著『昔は解けたのに・・・大人のための算数力講義』にまとめられており、一言で述べると「算数+α」の内容である。
以下、なぜ算数に関する内容を堂々と講義したかについて述べよう。
(以下略、続きはソースでご確認ください)
現代 2025.04.30
https://gendai.media/articles/-/151494