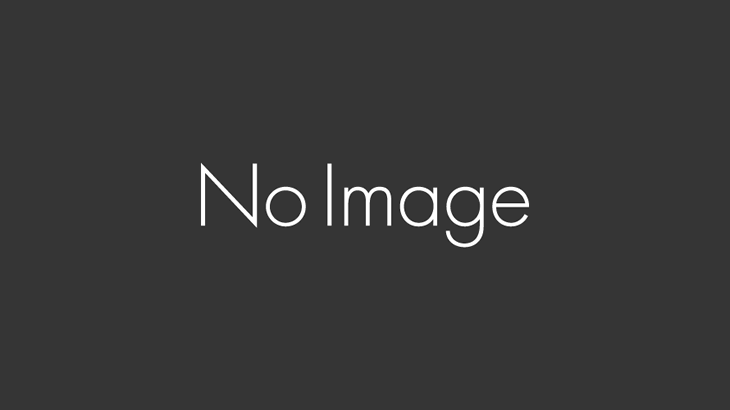あわせて読みたい
【厚労省】2012年実施の児童手当の使い道調査でデータ取り違え 2019年に「32%が遊興費」と誤報、本当は0.9% 実際は「子どもの将来のための貯蓄等」と判明し修正していたことが発覚
【厚労省】2012年実施の児童手当の使い道調査でデータ取り違え 2019年に「32%が遊興費」と誤報、本当は0.9% 実際は「子どもの将来のための貯蓄等」と判明し修正していたことが発覚

日本経済新聞によると

2019年11月15日
厚生労働省は15日までに、中学生以下の子どもがいる世帯に支給する児童手当に関する調査結果に誤りがあったとして内容を修正した。高所得者層の児童手当の使い道について、インターネット上の指摘から、データの取り違えが発覚した。調査結果は財務省が高所得者層への児童手当の見直しを要請する際の資料にも使われていた。
修正したのは世帯年収別の児童手当の使い道に関する調査。たとえばこれまで世帯年収1000万円以上の受給者は児童手当の32%を「大人のおこづかいや遊興費」に充てているとしていたが、正しくは0.9%だった。32%は「子どもの将来のための貯蓄・保険料」の誤りだった。取り違えが起きた原因は調査中としている。
これに伴い財務省も15日、財政制度等審議会(財務相の諮問機関)の資料を修正。世帯年収が高いほど児童手当が大人のお小遣いなどに使われているとの文言を「使う必要がなく残っている等の回答が多い」とした。児童手当の廃止を含む見直しを求める方針は変更なしとした。
[全文は引用元へ…]
以下,Xより
【kq 党推さんの投稿】
党推さんの投稿】
これはブチギレて良くない…?
データ取り違えで大人の遊興費になってるって報告にしてた、って、流石に作為を感じるよあと、残ってるんじゃなくて高校大学の為に残してるんじゃん。データ考察する気あんのか
児童手当の使い道、厚労省が調査結果修正 – 日本経済新聞 https://t.co/JcKQ0gaPTD
— kq
党推 (@kq97780659) February 11, 2025
あ、念のため。
2019年の記事です— kq
党推 (@kq97780659) February 11, 2025

これってアンケート結果の項目がまるっと間違ってたのよね。
正「子どもの将来のための貯蓄・保険料」が誤「大人のおこづかいや遊興費」になっていた。このアンケ作られたのは2012年で所得制限した年です。児童手当の使い道、厚労省が調査結果修正 – 日本経済新聞 https://t.co/jQIludP96b pic.twitter.com/4wuWQJL7wd
— ももんが子@減税+全ての増税に反対 (@momongaiyako) February 11, 2025
初コメ失礼します。
私は児童手当は保育園の費用に当ててますが…
正直消費税下げて貰った方が、間違いなく負担は減ります。
少子化対策が現状これでは何も少子化対策にはなっていません。
異次元の少子化対策って何だったのでしょうか?
子供を出汁に使うのはやめて貰いたい。
現に出生率減ってます…— パパ(´・ω・`) (@1207ktk) February 11, 2025
はじめまして
子どもをダシに負担増やされるのはしんどいし、消費税が下がったら絶対助かりますよね前は年少扶養控除という、0-15歳の子を扶養すると減税する制度があったんですが、政権交代の中で無くされてしまいました。他にも色々酷いことがあります。
子育て世帯はもはやマイノリティです
— kq
党推 (@kq97780659) February 11, 2025
ほんと、マジで貯金して何が悪いん?
奨学金で借金して社会に出せばいいと思ってんの?
大人の遊興費って何?
生活保護でもないのに使い方に文句つけんなよ
マジで上から目線で腹立つ
子供育てるのが罰ゲームになってんのはそなた達のせいだよ— 月と雨 (@qppJzr8j1WEyJf5) February 11, 2025
年金制度もそうですが、厚生労働省は嘘つきなんですね。
— そのへんのおじさん (@TaoHiker) February 11, 2025
引用元 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52212800V11C19A1EA4000/
みんなのコメント
- データ取り違えってレベルじゃなくて、完全に印象操作じゃないのか 財務省が児童手当削減のために都合のいいデータを使ったとしか思えない
- 本当はほとんどが貯蓄や子どものために使われてたのに、遊興費に使われてるってことにされてたのか こんなの詐欺みたいなもんだろ
- 児童手当を大人の遊びに使ってるって印象を広めて、削減の流れを作ろうとしたのか 子どもを育てるための制度をこんな風に扱うのは許せない
- 間違えましたで済む話じゃないだろ このデータを基に政策が進められたんだから、これで損をした家庭がどれだけあるのか考えたことあるのか
- 高所得世帯だからって、子どものために貯蓄してるだけなのに、それを「遊興費に使ってる」とか言われたらたまったもんじゃないな
- 修正しましたって簡単に言うけど、こんなデータを何年も放置してたってことが問題だろ 気づかれなかったらそのままにしてたんだろうな
- 誤報で児童手当のイメージを悪くして、削減しようとしてたなら、もう完全に確信犯じゃないか 財務省と厚労省の責任はどうなるんだよ
- 結局、子育て支援なんてやる気ないってことだな 少子化対策とか言ってるけど、やってることは子育て世帯を締め付けることばっかり
- 異次元の少子化対策って何だったんだよ こんなデタラメなデータで政策進めるくらいなら、最初からまともな支援を考えてくれ
- データを正しく扱えない時点で、もう政策を決める資格なんかないだろ こんなミスを許してたら、今後も同じことが起こるぞ
- 誤報を元に議論して、結局児童手当の縮小の流れを作ったなら、それを撤回しないとおかしいだろ このまま押し切るつもりか
- なぜか財務省の方針は変わりませんって、結局データの間違いなんて関係ないってことかよ もう削減ありきで進めてるだけじゃないか
- このミスが意図的じゃなかったとしても、結果的に子育て世帯に不利益をもたらしてるなら、責任を取るべきだろ
- データを正しく分析する気が最初からないんじゃないのか 高校や大学のために貯蓄してるのを、使う必要がないとか言い換えてる時点で怪しい
- 子どもを出汁にして増税や支出削減を正当化しようとしてるとしか思えない 少子化対策のためにやるべきことは他にあるだろ
- 消費税を下げれば確実に負担は減るのに、それは絶対にやらない 児童手当の見直しなんかより、まず税制を考え直せよ
- この間違いが今になって発覚したってことは、それだけチェック体制がずさんだったってことだろ こんなのが政策の根拠になってるとか恐ろしい
- どうせ他にもデータの取り違えとかやってるんだろ 国民が知らないだけで、同じようなミスが色々なところで起きてそう
- 修正したからもう問題ないって態度が腹立つわ 間違ったデータで議論を進めてた責任を誰も取らないのかよ
- こんなことを繰り返してたら、政府の発表なんて誰も信用しなくなるぞ もう自分で調べないと本当のことが分からない時代になってるな
編集部Bの見解
厚生労働省が2012年に実施した児童手当の使い道に関する調査で、重大なデータの取り違えがあったことが発覚した。2019年に公表された調査結果では、世帯年収1000万円以上の受給者が児童手当の32%を「大人のおこづかいや遊興費」に使っているとされていたが、実際にはわずか0.9%だった。32%という数字は、本来「子どもの将来のための貯蓄・保険料」に使われている割合だったという。
この調査結果は、財務省が児童手当の見直しを求める際の資料にも使われていた。つまり、「高所得世帯では児童手当が本来の目的以外に使われている」とする誤ったデータが、政策議論の根拠として用いられていたことになる。厚労省はこの誤りを認め、15日までにデータを修正したが、すでに政策に影響を及ぼしていた可能性が高い。
この発表を受け、多くの人が疑問や怒りの声を上げている。「これはブチギレて良い案件では?」「単なるミスではなく、作為的な意図を感じる」といった意見が見られるのも当然だろう。調査結果のデータ取り違えというレベルの話では済まされず、政策決定に大きな影響を及ぼしていたことを考えれば、単なるミスではなく「都合の良いデータを作り出したのではないか」という疑念すら浮かぶ。
特に問題なのは、「大人のおこづかいや遊興費に使われている」という誤った情報が拡散されたことで、児童手当が無駄に使われているかのような印象を与えてしまったことだ。実際には、高所得世帯ほど児童手当を「子どものための貯蓄や保険」に回しているのが正しいデータだったにもかかわらず、それが歪められた形で公表されていた。
さらに、財務省は今回の修正を受け、「世帯年収が高いほど児童手当が大人のおこづかいなどに使われている」という表現を「使う必要がなく残っている等の回答が多い」に変更した。しかし、この言い換え自体も問題をはらんでいる。「使う必要がなく残っている」と言うが、実際には高校や大学進学のために貯蓄している家庭が多いのではないか。そもそも児童手当は、子どもの成長に合わせて使うべきものであり、全額をすぐに使わなければならないものではないはずだ。
この問題を受け、「私は児童手当を保育園の費用に当てているが、正直消費税を下げてくれた方が負担は減る」「少子化対策として児童手当が見直されているが、今の施策では何も効果が出ていない」「異次元の少子化対策って何だったのか」といった意見も多く見られる。
政府は少子化対策として児童手当の拡充や給付の見直しを進めているが、今回のようなデータの誤りが発覚すると、その政策の根拠そのものが疑わしくなる。誤ったデータを元に議論を進められていたとすれば、国民の信頼を損ねるのは当然のことだ。
また、そもそも児童手当をめぐる議論は、「子どもを産み育てやすい環境を作るための支援策」として行われるべきだが、今回のデータ誤りによって、制度の意義そのものが誤解されかねない状況になっている。
この件に対し、「データも正しく作れない、基本的なミスをチームで見つけられないレベルの人たちが政策を決めているのは問題だ」「子どもを出汁に使って財政の話を進めるのはやめてほしい」「結局、児童手当を削減したいだけでは?」といった厳しい意見も出ている。
そもそも、こうしたデータの誤りがなぜ発生したのか、明確な説明が求められる。厚労省は「取り違えの原因を調査中」としているが、調査結果を公表する前にしっかりとチェック体制を整えておくべきではなかったのか。政策決定に関わる重要なデータが、このような基本的なミスで歪められていたというのは、極めて深刻な問題だ。
今回の件を受けて、政府はどのように対応するのかが問われる。単なる「修正」で済ませるのではなく、政策決定のプロセス全体を見直し、今後同じような誤りが発生しないような仕組みを作ることが求められるだろう。
また、国民としても、こうしたデータの誤りが政策にどのような影響を与えているのかを注視し、政府の説明をしっかりと求めることが重要だ。政策の根拠となるデータが誤っていた場合、その政策自体が見直されるべきだからだ。
少子化が深刻化する中で、政府が本気で子育て支援を考えているのならば、児童手当をめぐる議論も正確なデータに基づいて行われるべきだ。今回の件を単なるミスで済ませず、政策全体の在り方を見直すきっかけにするべきではないだろうか。
執筆:編集部B
最新記事
-
【厚労省】2012年実施の児童手当の使い道調査でデータ取り違え 2019年に「32%が遊興費」と誤報、本当は0.9% 実際は「子どもの将来のための貯蓄等」と判明し修正していたことが発覚
-
大阪・大東市議宅が全焼し焼け跡から遺体、12歳長女と連絡取れず 市議と次男も負傷
-
動画の男性『トランプさん、不法移民対策をしてくれなかったら俺は仕事を失っていた。本当に感謝します!』→ネット「移民は仕事を奪わないなんて嘘だ。日本も同じ道を辿る。政治家は自国民を守れ。」
-
中国外務省「任務完了」尖閣諸島周辺に設置していたブイを移動させたと明かす
-
【悲報】USAIDさん、年間予算6兆7000億円のうち、飢餓など命に関わる支援活動はたったの5%で、左翼、ジェンダー政策(LGBT)、共産主義者社会主義者への資金提供が95%だった…