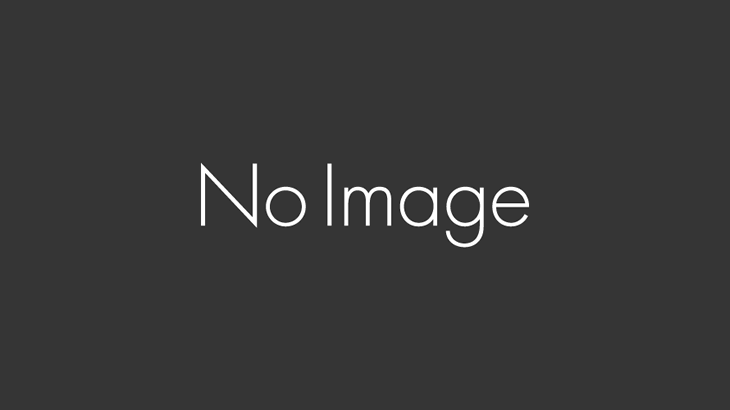あわせて読みたい
動画【X民】「テレビは噓ばかり」 結構この認識広がって来てるのかな?
動画【X民】「テレビは噓ばかり」 結構この認識広がって来てるのかな?

以下,Xより

【たるとさんの投稿】
「テレビは噓ばかり」
結構この認識広がって来てるのかなpic.twitter.com/V3w8VJ3a4C
— たると (@tarutora17) February 10, 2025
>「テレビは噓ばかり」
ダマせてると思っているのは作り手側 残念でした。
— kibun (@kibun79316998) February 11, 2025
「テレビは噓ばかり」
そりゃこの前の衆院選でブ-ビ-だったデマ太郎を
「平均的に経験、外交力、世論指示、議員指示、刷新感、バランス良い」
と偏向報道したら、おばちゃん達も気がつくと思います、、、
https://t.co/AyHsOU5v2I
— Yを@ライドシェア絶対反対
(@Y5915815445413) February 11, 2025
嘘というより肝心なことを言わない隠ぺい体質が目立ってきた印象ですね
特に国家に不都合なことを放送・報道しなくなりましたよね
政府に批判的なキャスター、コメンテーターは使われなくなり番組そのものもなくなってしまうなど、まるで言論規制が敷かれた某国々のよう— 原条 伏羲 (@7UTSrHP7KS0YZEv) February 11, 2025
テレビは全く必要ない時代に突入したね。
これはこれで仕方ない。
メディアの自業自得。
今はテレビより勝れた物が沢山あるし。
ましてや嘘を報道したり都合が悪いと報道しないテレビなんて誰も見向きもしない。
日本国民の老若男女がそれに気づいただけ— 犬好き@婆サブ垢
(@Dachshu55979189) February 11, 2025
あくまでの台本がありスポンサー、株主のためのTVショー。
右から左に流してる分にはいいけど真剣に見るもんじゃないのが今のオールドメディアだと私は認識きてます。その中でもいい情報があればしっかり見ます。— Nagisa (@Nagisa2864) February 11, 2025
「テレビは噓ばかり」 結構この認識が広がって来たか
よかった
SNSより先ずテレビやテレビ局、新聞社の偏向報道、偏向発言の規制が必要
それと不要テレビ局の閉局が必要— サイハン (@buron2011) February 11, 2025
引用元 https://x.com/tarutora17/status/1888966782276476973?s=51&t=y6FRh0RxEu0xkYqbQQsRrQ
みんなのコメント
- テレビの報道を見ていると、どう考えても一方的な内容が多い。ネットでは事実と違う情報が次々と暴かれているのに、テレビは都合の悪い部分を隠して放送しているようにしか思えない。
- 昔はテレビが唯一の情報源だったから、視聴者も信じるしかなかった。でも今はネットがある。テレビの嘘がすぐにバレる時代になったのに、未だに同じやり方を続けているのは時代遅れとしか言いようがない。
- テレビの偏向報道がひどすぎて、もう見る気がしない。ある特定の意見ばかりを取り上げて、反対意見は完全無視。公平な報道をする気がないのなら、報道番組なんて名乗るなと言いたい。
- 結局、スポンサーや一部の団体の意向を忖度しているから、テレビの報道は信用できない。都合の悪いことは報じず、特定の立場を優遇するやり方は明らかにおかしい。
- 政治ニュースを見ていると、明らかに一部の政党に有利な報道が多すぎる。公平な視点が欠けているし、世論を誘導しようとしているようにしか思えない。こんなものを見て、何を信じればいいのか分からなくなる。
- テレビの影響力は確実に落ちている。かつては絶対的な存在だったが、今はネットで検証されることで嘘がすぐにバレるようになった。それでもまだ「自分たちが正しい」と思っているのなら、本当に終わっている。
- 大手メディアは「ネットの情報は信用できない」とよく言うが、それを言うならまず自分たちの報道姿勢を正せばいい。テレビの報道が信用できないから、ネットで真実を探す人が増えていることに気づいてほしい。
- ニュース番組のコメンテーターがいつも同じ顔ぶれなのが不自然すぎる。結局、意見の多様性を認めるつもりがなく、視聴者に特定の考えを植え付けようとしているとしか思えない。
- テレビは都合のいい情報しか報じない。問題の本質を隠して、表面的な話ばかり繰り返す。こんなことを続けていれば、視聴者が離れていくのも当然だろう。
- 何か問題が起きたとき、テレビが伝えるのは決まって一方向の意見だけ。ネットで調べると、全然違う事実が出てくることも多い。そうなると、もうテレビの情報なんて信用できない。
- 視聴率が下がり続けているのに、テレビは「なぜ若者がテレビを見なくなったのか」と言い続けている。答えは簡単で、偏向報道がひどすぎて信用を失ったからだろう。
- 一部のメディアは、自分たちが世論を作っていると勘違いしている。昔はそうだったかもしれないが、今は違う。ネットの情報がある時代に、印象操作だけで世論を誘導するのはもう無理がある。
- テレビで「ネットの情報に騙されるな」と言われても、テレビの報道こそが偏っていることがバレてしまっている。都合のいい情報だけ流すやり方は、もう通用しない。
- 特定の政治家に対しては徹底的に叩くのに、別の政治家の問題はほとんど報じない。このダブルスタンダードがあまりにもひどい。公平な報道とは何なのか、もう一度考え直すべきだ。
- テレビのニュース番組は「専門家の意見」と言いながら、実際には特定の意見を持った人しか出演させない。違う意見の専門家もいるはずなのに、なぜか出てこないのは不自然だ。
- 昔はテレビが絶対だったが、今はSNSがあるおかげで情報の真偽を確かめられるようになった。結果として、テレビの報道が信用できないことがどんどんバレている。
- 視聴者を舐めているとしか思えない内容の番組が増えた。ニュースもワイドショー化して、冷静な分析ではなく、感情論ばかり。これでは信頼されるはずがない。
- スポンサーの意向に従うしかないから、テレビは本当に伝えるべきことを伝えない。こうした体質が続く限り、ますます視聴者離れが進むだけだろう。
- 何か大きな事件が起きると、テレビとネットで報じられる内容が違いすぎる。どちらが正しいのかを自分で判断する必要がある時代になった。テレビを盲信する時代はもう終わっている。
編集部Aの見解
「テレビは嘘ばかり」という認識が広がっていることを考えると、今の時代、情報の信頼性について改めて考えさせられる。かつて、テレビは情報の中心だった。ニュースもバラエティ番組も、テレビが発信する内容を疑うことなく受け入れるのが普通だった。しかし、今は違う。X(旧Twitter)などのSNSが普及し、多くの人がテレビの情報をそのまま信じなくなっている。
特に最近は、テレビ報道に対する疑念がますます強まっているように感じる。ニュースを見ていても、報道の仕方に偏りを感じることが多い。同じ出来事でも、特定の意図を持って編集されたり、都合の悪い部分は報じられなかったりする。こうしたやり方に違和感を覚える視聴者が増えた結果、「テレビは信用できない」と考える人が増えてきたのではないか。
テレビが絶対的な影響力を持っていた時代と比べると、今は情報の受け取り方が変わっている。ネットが普及し、個人が自由に情報を発信できる時代になったことで、テレビの情報をそのまま鵜呑みにする必要がなくなった。むしろ、テレビとネットの情報を比較し、どちらが正しいのかを自分で判断する人が増えている。
特にX(旧Twitter)では、テレビの報道に対する批判が頻繁に見られる。あるニュースに対して「テレビではこう報じられているが、実際にはこうだ」といった投稿が拡散されることも多い。こうした情報が蓄積されることで、「テレビは偏っている」「真実を隠している」という認識が広がっているのではないか。
もちろん、テレビの報道がすべて嘘とは言わない。しかし、都合のいいように情報を編集し、一方的な見解を押し付けるような報道が多いのは確かだ。特定のイデオロギーを持った番組作りが行われることで、視聴者に偏った印象を与えることもある。その影響は決して小さくない。
かつてはテレビが社会の常識を作っていた。しかし、ネットの登場によって、それが覆されつつある。以前なら、テレビで報じられた内容は「事実」として受け止められていたが、今は違う。視聴者がネットを通じて自ら調べ、テレビの報道がどこまで正確なのかを検証する時代になった。
この流れが進んでいることは、テレビ業界にとって大きな問題だろう。かつては絶対的な影響力を誇っていたテレビが、今や視聴者に疑念を持たれる存在になっている。これにより、テレビ離れが加速しているのも事実だ。視聴率が低迷し、広告収入も減少。ネットメディアに押され、テレビの存在感は年々薄れている。
では、なぜここまで「テレビは嘘ばかり」という認識が広がったのか。一つの要因として考えられるのは、報道の姿勢だ。例えば、政治報道において、特定の政党や政治家に対して明らかに好意的、もしくは敵対的な報じ方をすることが多い。これが、視聴者の不信感を招いているのではないか。
さらに、テレビはスポンサーや特定の団体の影響を受けやすいという問題もある。テレビ局は広告収入によって成り立っているため、大手企業や政府の意向を無視することができない。その結果、特定のスポンサーに不利な情報は報じられなかったり、逆にスポンサーの意向に沿った内容が強調されたりすることがある。こうした事情を知る人が増えたことで、テレビの信頼性が低下しているのではないか。
加えて、視聴者が賢くなったというのも大きい。SNSを利用することで、多くの情報に触れる機会が増えた。テレビだけが情報源だった時代と違い、今はネットでさまざまな意見を比較し、判断することができる。そうした環境の中で、テレビの情報がどこまで信頼できるのかを疑う人が増えているのも当然のことだろう。
この流れは今後も続くだろう。テレビの影響力はさらに弱まり、ネットが主流のメディアになっていく可能性が高い。特に若い世代は、テレビをほとんど見ないという人も多い。その代わりに、XやYouTubeといったネットメディアを活用し、自ら情報を取捨選択している。こうした変化が進めば、テレビの存在価値はますます問われることになる。
とはいえ、テレビが完全になくなることは考えにくい。依然として影響力を持っているし、高齢者を中心に根強い視聴者もいる。しかし、今までのように「テレビが報じたこと=事実」とはならない。視聴者が批判的に見るようになったことで、テレビ側も情報の扱い方を変えていかざるを得なくなるだろう。
今後、テレビが信頼を取り戻すためには、公平で客観的な報道を心がけることが不可欠だ。特定の立場に偏ることなく、事実をありのまま伝える姿勢が求められる。そうでなければ、視聴者の離反は止まらず、ますます「テレビは嘘ばかり」という認識が広がっていくだろう。
執筆:編集部A